【メモ】
悲しい感情を自分の中で開放させて、誰はばかることなく思い切り泣いたら、少しは気分がすっきりするでしょう。村上龍の本を読んでいると、胸が締めつけられるような、悲しいような、切ないような、そんな気持ちになることがあります。でも、そんな気持ちにさせられるのと同時に、心の中で何かが動いた分、読んだあとで、自分の心がすっきりと軽くなったようになっていることに気が付かされることもあります。
人間や社会の中に無数に存在するネガティブなもの、不条理なものを、正面から見据えるというのは中々難しいものです。
僕のような弱い人間は、すぐに逃げ出して、そういったものから目をそむけてしまう。
でも、そういったものを正面からしっかりと見据えることが出来るからこそ、同時にこの社会が持っている素晴らしいものをみることもできるのだろうな、と思うわけです。
村上龍は、文章を通して僕に「強さ」を貸し与えてくれます。作家としての彼の「強さ」を借りた「弱い僕」は、自分のリアルな目では見ることができないものを彼の文章を通して見て、いっとき感情を開放させ、何かを感じることができます。
万人にあう文章なのかどうかは別として、少なくとも僕にとっては読む価値のある本でした。
【本文書き出し】
”序章 直径十センチの希望
内山秀樹は、自室の窓を被う黒い紙に直径十センチほどの丸い穴を開けた。コンパスを使って円を描き、カッターナイフでえぐり取った。その穴は、ちょうどカメラの望遠レンズの大きさだったが、昔買ったカメラを手にする気になったわけではなかった。
引きこもりを始めてから一年半が経とうとしている。外出するのが苦痛になって、窓に黒いケント紙を貼った。雨戸が無いのでカーテンだけでは外光が洩れる。光が部屋の中に差し込むのが我慢ならなかった。黒のケント紙が少しずつ湿気で剥がれてくると、上から修復した。今では、黒い紙は何重にも自分と外を遮断している。
外の音も聞きたくなかった。特に下の道を通る人の話し声や、挨拶を聞くのもいやだった。外側に大勢の人間たちがいて、会話や仕事や恋愛をしている。窓に黒いケント紙を貼っても、そういう現実を完全に遮断できるわけではない。そんなことはよくわかっていた。だが自分以外の人々は、逃げずに現実を生きていて、いろいろな場所へ出かけ、さまざまな他人と出会いながら人生を楽しんでいるのだ。そういったごく当たり前の生活を送る人間たちの声を聞きたくなかった。
インターネットの引きこもりサイトの掲示板では、五年とか十年とか、秀樹よりもはるかに長い期間引きこもりを続ける人の書き込みを見ることができる。みんな他人を恐がっている。自分一人ではないと思って秀樹は少し安心できる。秀樹と同じように窓外の他人の話し声を聞いたり、姿を見るのがいやだという人も多かった。ただ彼らの書き込みを見て不安になるのは、他の人間の匂いのようなものを避け続けると、生の人間をたとえば映画とか写真とかで見るのも恐くなってくるらしい。ある人は、映画とかテレビではアニメしか見ることができないし、雑誌でも漫画しか読めなくなったと書いていた。生の人間が写っているページはあらかじめ親に切り取って捨ててもらうらしい。
まだ引きこもって一年半だ、と秀樹は自分に言い聞かせ、安心しようとする。まだ二十一歳だし、インターネットの引きこもりのページに登場する三十歳とか四十歳の引きこもりに対しては、優越感のようなものを感じることがある。でもおそらくあっという間なのだろうと思って恐くなる。引きこもって半年くらいは、親と口論したり、アルバイト情報のサイトにアクセスしたり、古い知り合いにメールを出したりして、それなりに時間が過ぎていくのを感じることができた。安定剤を飲み始めたころから、体がだるくなり、頭がぼーっとして、時間の経過が不確かになってきた。薬のせいなのか、昼夜逆転の生活のためか、からだの反応が鈍くなって、その後の一年は、夢の中にいるような感じのままあっという間に過ぎてしまった。
夕方に目を覚ますと、秀樹はまずパソコンを立ち上げて、ネットにつなぎ、メールをチェックする。届いているのはいくつかのメールマガジンだけだ。誰からもメールなんか来るわけがない。母親経由で、精神科医に言われた。何でもいいから自分で小さな目標を作って、それを達成したら自分をほめるようにしなさい。二日に一度コンビニに牛乳を買いに行く。メール友だちを作る。朝の七時や八時ではなく、せめて深夜の三時までには寝るようにする。暗くなってから家のまわりを散歩してみる。家族に優しい言葉をかけてみる。いろいろ目標を立ててみたが、何一つ実行できていない。
焦りはひどくなるばかりだ。このまま死んでいくんだな、と一人で呟いたりするようになった。あきらめてはいけない。そういう風にネットの掲示板などにはよく書いてある。また、焦らずにしばらく休んでもいいんだよ、という風にも書いてある。休むのはいいが、あきらめてはいけない。そういうことだ。簡単ではない。休むこととあきらめることの区別が秀樹にはわからない。あきらめるな、というのと、休んでもいいんだよ、というのをどう関係づければいいのかわからなかった。
そんなことはもうどうでもいいから楽になりたいと思うと、からだと脳が溶けていくような、気味の悪い、それでいて気持ちがいい、変な気分になった。このままでは神経がおかしくなってしまうと思ったときに、秀樹は、黒いケント紙に十センチの穴を開けることを決めた。他にやることが見つからなかった。二時間かけて、カッターナイフで穴を開けた。十センチの穴から、カーテンを通して、日差しが部屋に入ってきた。しかし秀樹はすぐにその穴から外を覗く勇気がなかった。
【表紙及び冒頭5ページ】
【基本データ】
幻冬舎文庫
平成15年4月15日初版発行
村上龍「最後の家族」
ISBN4-344-40357-6
<!–
”この本、読ませてみたいな”と思ったら
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/3fdc5f3d7562764998cb0fcb159c68bb-600x600.jpg)
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/3fdc5f3d7562764998cb0fcb159c68bb-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/d4ee692ecff9575122e8ea39961d0ce5-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/1fa67f7c3c1f02d900e549bf35f4ed70-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/5829e1d96010aedd978b693231c6e301-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/18c016c3253fe94c01732977e96a44e3-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 村上龍「最後の家族」 本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/b69d8d2eaeccef6401525ca8d922dd6f-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/26842a450d4c17ddcbdb3de87254bdbf-600x600.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/70df16c7b8e41b85a6a8c8ae8f99d7c6-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/26842a450d4c17ddcbdb3de87254bdbf-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/87f48273377084b36eab73a3de90ebd9-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7277182dc857fd4e8bed22c2d3ddc629-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e492708652a6e887dc1c56175558a42c-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/880972423b2a1c382763f64e56be7197-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/46c46d71e87638fc9705d221dc608dd7.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c14ae0c0ef02b71aa20abe673d6690bb.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/46c46d71e87638fc9705d221dc608dd7-600x600.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/46c46d71e87638fc9705d221dc608dd7-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7337a81344f0e8cec9ce29be40718b58-180x320.jpg)
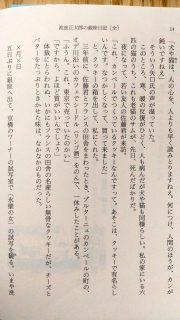
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/597c59e7972276eacb1d89fba2fd2862-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/2e3192b479772157381328251c369546-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/3e8d85076dd1e973cf04c98673874e00-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/26842a450d4c17ddcbdb3de87254bdbf.jpg)