【メモ】
・池井戸潤作品を沢山読みすぎて、却ってよくわからなくなってきたけれど、「検査」「監査」的なシーンが沢山ある気が。そして、このシーンを描写する中で、銀行という組織の「ある一面」を上手く読者に伝えている気が。
・「企画部」と「人事部」は本部内のライバル同士。
・「企画部」という部署名もよく出てくる気が。「本部の企画部」というのも、銀行という組織を象徴するような一部門なんだろうか。著者もそこに近い部門にいたんだろうか。でも、慶応卒とはいえ働き出してたかが10年目くらいにはこの作品を書いているわけで、出世コースに乗ってたとしてもぺーぺーの期間が終わってちょっと経ったくらいだったんだろうが。
・派閥。僕の所属している世界も財閥系の☓☓とかなわけだが、少なくとも、こんな風に派閥がどうこうと表立ってストレートなものは無い。でも、言われてみれば「◯◯常務がうんチャラかんちゃらで」みたいな、お偉いさんのどーでも良い好き嫌いが現場での仕事の仕方に関わってくることはたまにあって、どこの世界でもそういうのはあるかな、と。
・という様な、「銀行という組織」を如実に、端的に、特徴的に表すものが、わかりやすく描かれているところが池井戸作品のいいところ。これは銀行がメインステージにならない作品でもそう(大抵は銀行が絡んでくるけど)。そういう「ベース」が上手く書けていて、そこにまず上手に引き込んでもらえるからこそ、読者はそこで起きる事件にどんどんとのめり込んで行ける。書き方が上手いし、自分が上手く書けるものをよくわかってらっしゃる。
・仕事好きな人向け。
【書き出し】
”第一章 死因
1
鉄扉を開けると、七月初旬のむっとする空気が足元になだれ込んできた。梅雨空はどんよりと重く、ここのところ降ったり止んだりという天気が続いている。午前十時。私は、融資先を訪問するために銀行ビルの裏口を出て、店から少し離れたところにある駐車場へ向かうところだった。土、日は人でごった返す渋谷も、平日の午前中となると街の人出はまだ少ない。とくに東急プラザのある表通りから一本入ったこの辺りは閑散として、回収前のゴミが収集場所から道路に溢れている。
私は、青い半袖のシャツにタイを結び、チャコール・グレーの上着を腕に掛けて歩いていた。持ち物はいつものように手帳一冊だ。たばこを点け、古本屋のシャッターが開いて顔見知りの主人がよっ、と手をあげるのに応え、その横のちっぽけなギャラリーに展示されている絵を見ながらストリップ劇場がある坂道の手前を左に折れる。
貸事務所が並ぶ通りの先を、見慣れた小太りの後ろ姿が歩いているのが目に入った。この蒸し暑いのにきっちりと上着を着こみ、左手に大きく膨らんだ重そうな黒鞄を提げている。軽装でおそよ銀行員らしくない私と違い、こちらはどこから見ても典型的な銀行員にしか見えなかった。
「坂本—!」
声を掛けると、ふっくらとした丸顔がはっと振り返った。物思いにふけっていたのか、普段温厚な男にしては珍しく表情が硬い。面白くもなさそうに指で眼鏡のフレームを押し上げ、右手に握っていたハンカチを額に当てながら呟いた。
「なんだ、伊木か」
私は足を早め、いつになく無愛想な同僚の横に列んだ。
「回収か」
「ああ。でかいぞ」
いったん立ち止まり、また歩き出す。横顔に緊張感が見て取れ、普段なら飛び出してくる冗談のひとつもない。
「今日はどこ?」
坂本は答えの替りに、にやりと笑った。
「なあ、伊木—」
歩きながら私の肩に腕をまわし、急に悪戯っぽい目でこちらを覗き込む。
「これは貸しだからな」
妙なことを言った。
「貸し?」
「いまにわかる」
坂本は丸顔を空に向けて高笑いしたが、次の瞬間にはいま笑ったことすら忘れてしまったかのような真面目腐った顔でさっさと自分の車を目指す。急いでいるのか、私との距離はどんどん開いていった。
一区画歩いた角に、桝井屋ビルと書かれた看板のかかった古ぼけた建物があり、その横が銀行専用のパーキングだ。二十台ほど入る小さなスペースで、業務用車と一般来店客の車両が兼用しているため業務時間中はいつも満杯に近い。まだ比較的早い時間なのに、空いている駐車用の区画はもう二つ、三つしかない。
坂本はそのまま足早にゲート脇を通り抜け、私が駐車場に着いたときには業務用の三菱ミニカを勢いよくバックで出していた。窓が開いた。
「まあ、見てろ」
そう言い残すと、レンガを敷き詰めた商店街の道路を国道246号線方面へと消えて行った。
2
坂本を見送ってから、どこかの下手くそがへこませたままになっているミニカのドアを開けた。顔をしかめたくなるほど車内の空気は熱く膨らんでいる。腕を伸ばしてまずエンジンをかけ、しばらくドアを開け放しながら、エアコンをフルまで上げて手帳を上着と一緒に助手席に放り込んだ。軽装だが、融資の案件を拾ってくるのにそれ以外必要なものなど何もないというのが、私の持論である。銀行のマニュアルによると、外訪員は黒い業務カバンに集金帳や印鑑を持ち歩くことになっているが、そんなものを持っていたら、ただの集金屋にされてしまう。
窮屈な運転席に座ると、熱をためたビニールシートが尻と背中にぺたりとくっついた。気色悪いのを我慢して床から付き出したマニュアルのギアをローに入れ、渋谷駅南口の交差点を左に折れて松濤方面へ向かう。松濤から富ヶ谷、南平台の一角が私の担当エリアだ。東急本店の脇を抜けていき、旧山手通りを右へ曲がった。
どこへ行かなければならない、という予定はない。適当に担当先を回り、「金を貸してくれ」と言ってくれる会社を探すのが私の仕事である。駅前のいつも混雑している道路に車を入れながら、頭の中で数軒の訪問先をリストアップした。私の担当は全部で五十社近くあるが、そこに一ヶ月に一度は顔を出すというのが、あってないような仕事のルールである。
この日、富ヶ谷の鉄鋼問屋を皮切りに、午前中かけてその界隈を彷徨き三軒ほどまわった。結果は、どれも空振り。ただ、成果がないのは別に珍しいことではない。新規融資の話など、二、三十軒当たってみて、一つあるかないか。そんなものだ。しかも、ある程度金額の張った話ともなるとさらに限られる。
言い訳めくが、融資担当としては新しい貸し出しの話がなくても定期的に取引先に顔を出して社内の様子を見てくるのも立派な仕事である。たとえば経理部長のデスクにサラ金からの計算書がないか観察したり、階段に死蔵されている製品が野積みになっていないか、工事業者であればスケジュール・ボードに書き込まれた受注工事状況が減っていないか、そんなことを見てくる。製造業者であれば機械の年式がどの程度のものかチェックするし、社員の電話対応やトイレの清掃状況、社長の金回りを見るために車のタイヤが減っていないかといったことも見る。取引祭の業況判断のためにマニュアル化された銀行の支店業務には、こういう地道な仕事も含まれるのだ。
昼過ぎ、三軒目になる設計事務所の経理担当部長との面談を適当に切り上げると、私は徐々に渋滞してきた山手通りから支店に戻った。昼食をとり、何もなければ午後からまた取引先を回る。そんな仕事が延々と続くわけだ。格別楽しいわけではないが、苦痛でもない。そんな仕事である…”
【表紙及び冒頭5ページ】
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7acbbbd425e5b26784e40790cec66b8e-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/568915458f31e71b4cc0d2c9f85e8469-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8a9cc9d5e3e20eacab99f7a0fd74fe3f-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/a45e5bdd66128be187843fe1f35e8720-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/df16c82afd8de2b248066899a5b13034-180x320.jpg)
【基本データ】
講談社文庫
2001年6月15日 第一刷発行
池井戸潤「果つる底なき」
ISBN4-06-273179-7
<!–
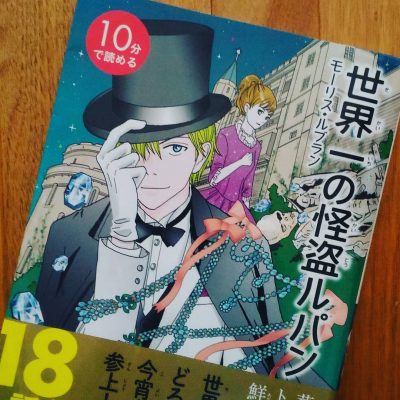
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/b5aaa0ad46cc617262786fc9bf49ba2e-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』目次1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4dc4cae276d5cd4836a9ec23b2f816c6-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』目次2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/657fa2a0c82f5942199d665e802ce54b-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』目次3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c4bc87721d648dc839de9f28c2e7a1b4-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』目次4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6e515ac9ec3cd4ffd10c7109059ebbab-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』タイトル_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8544e607a206bc4ad42aec45f1005f49-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb987f73b5abbb59bfd287a7ad50bad3-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/fc99686317b73b63b7604538ef6b9b4f-180x320.jpg)
![モーリス・ルブラン『10分で読める 世界一の怪盗ルパン』本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4e4f0c183a2339ce3616f8b9aebe0ea2-180x320.jpg)
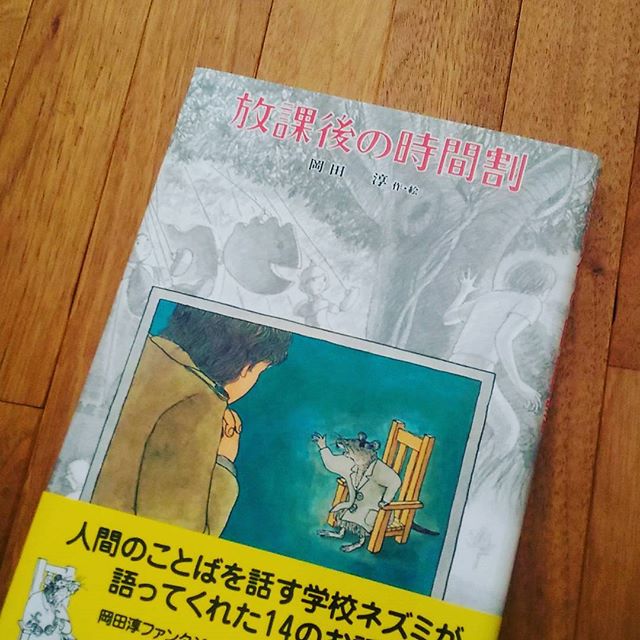
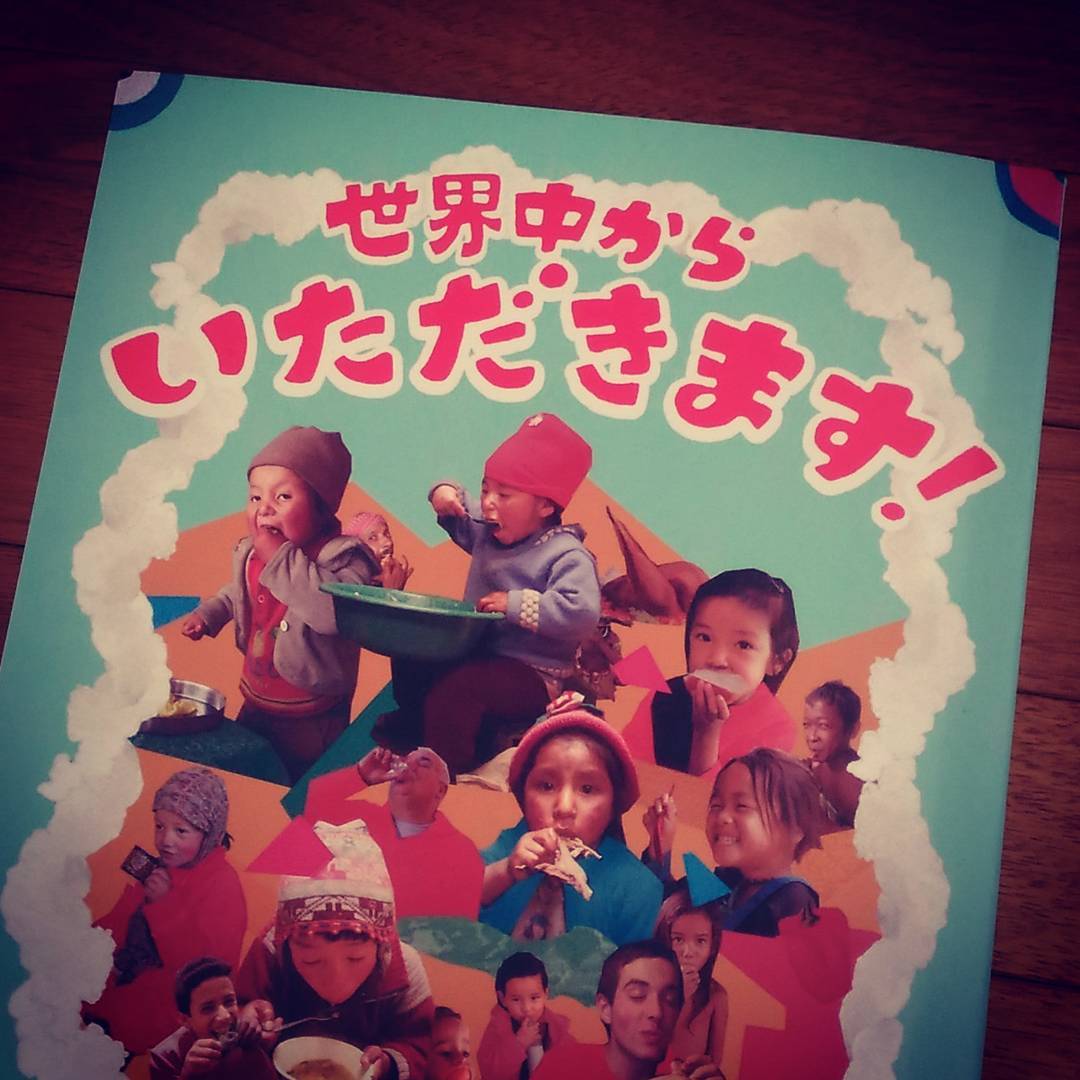
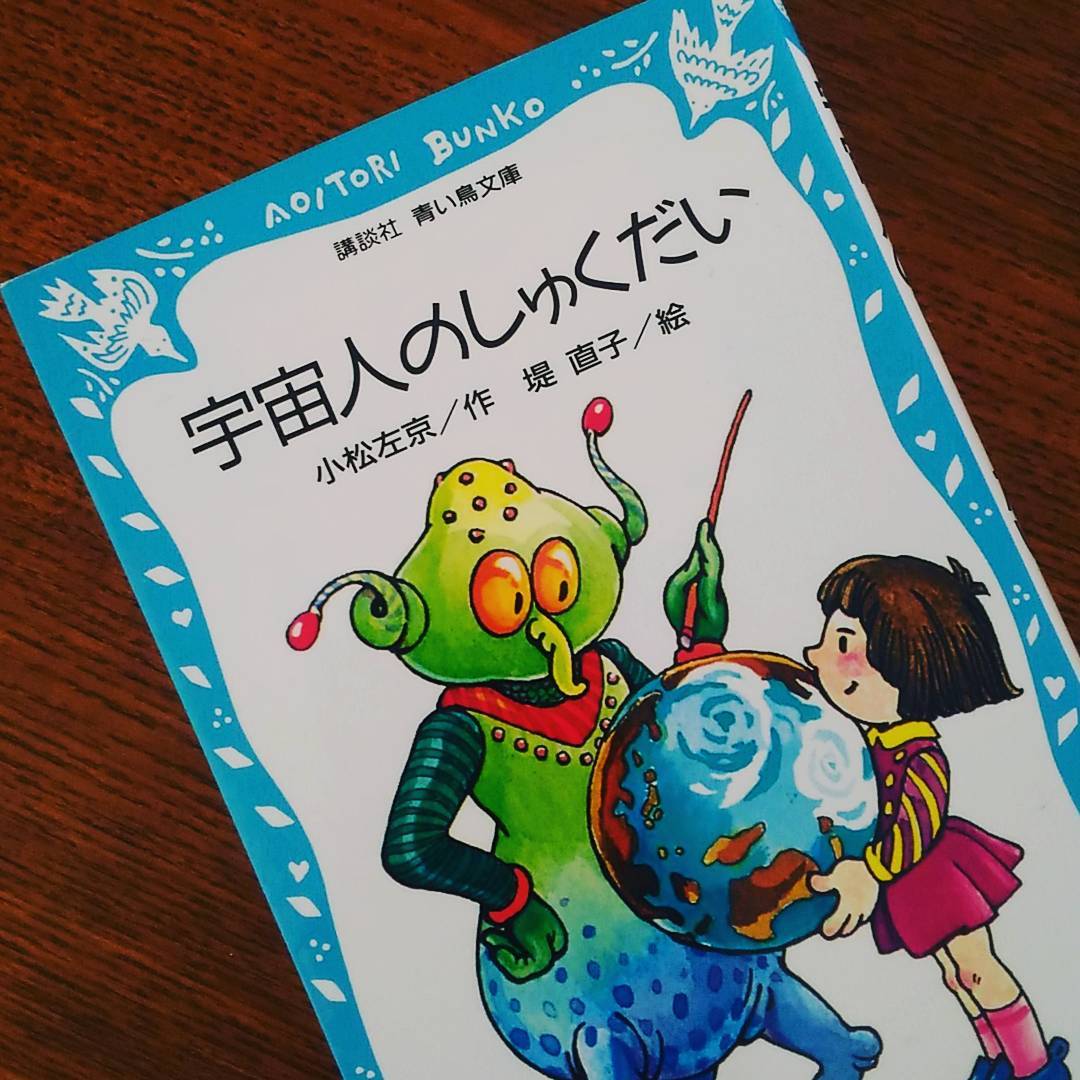
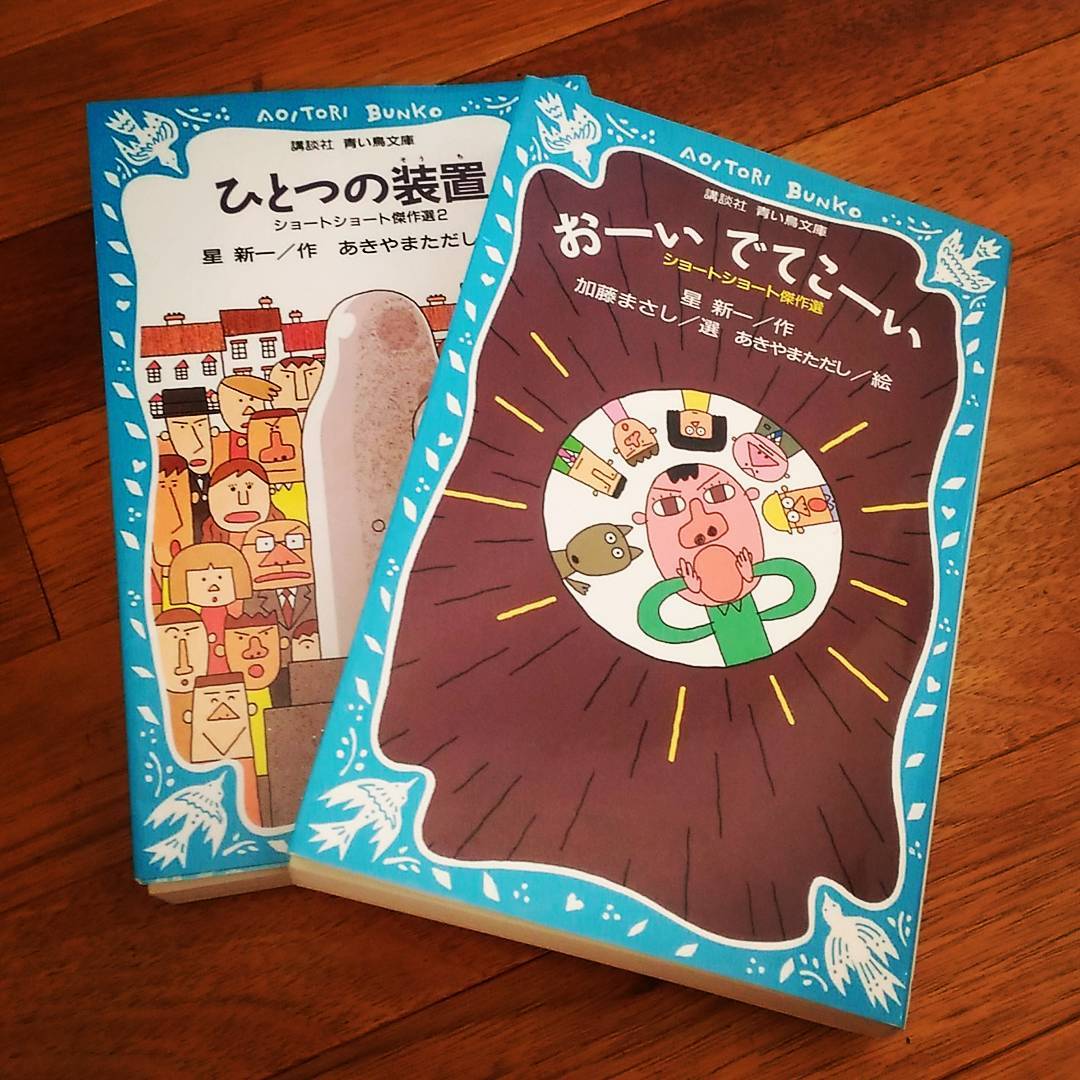

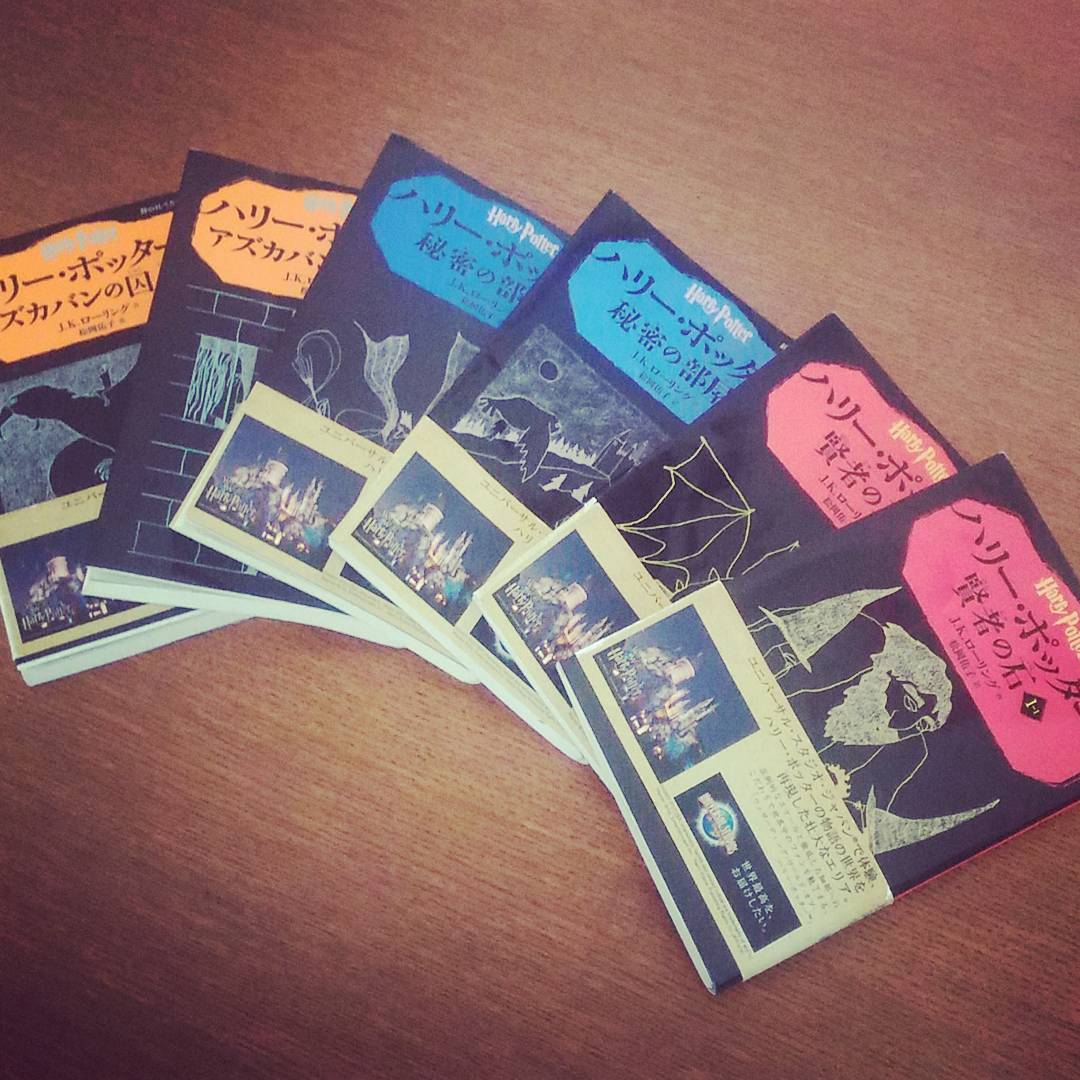
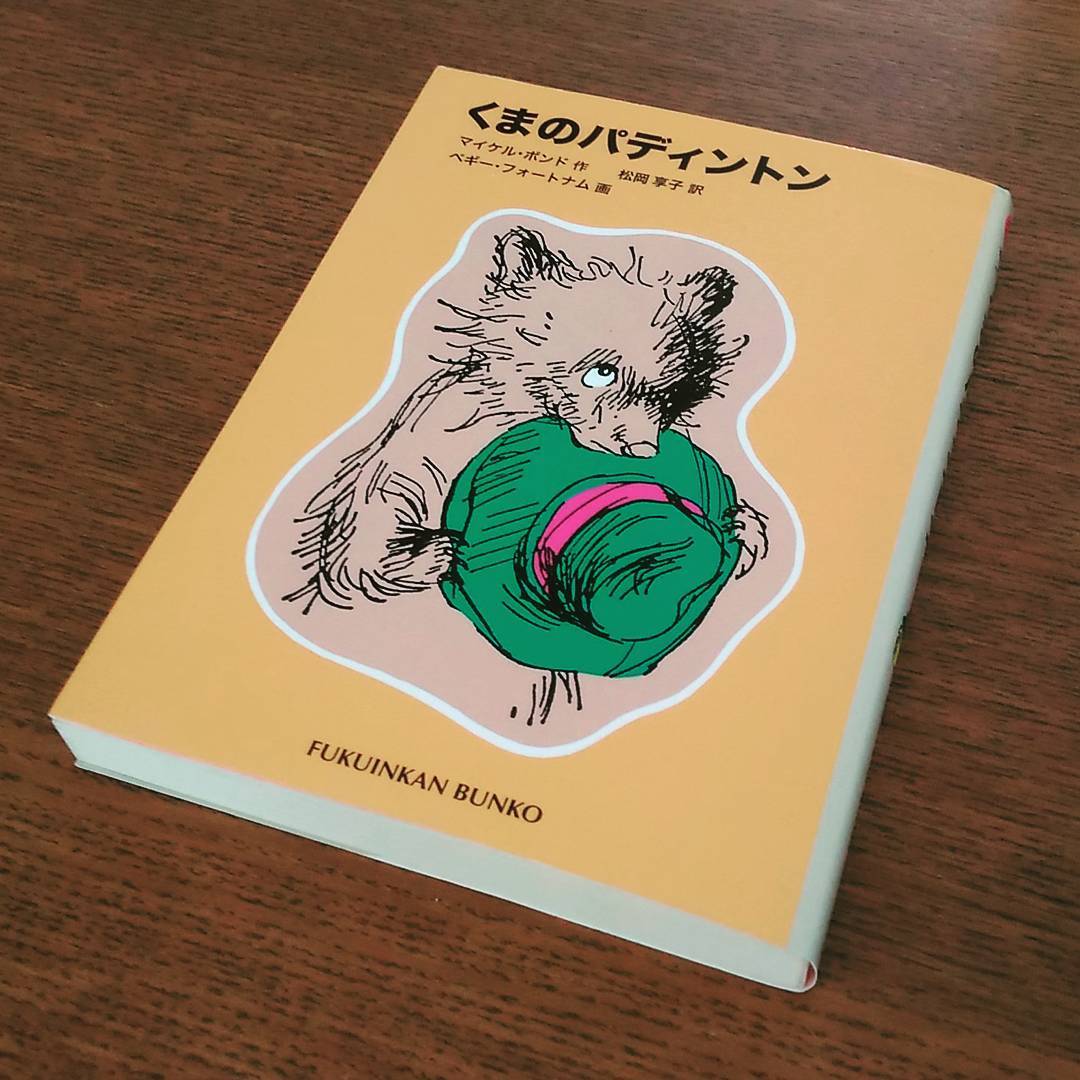
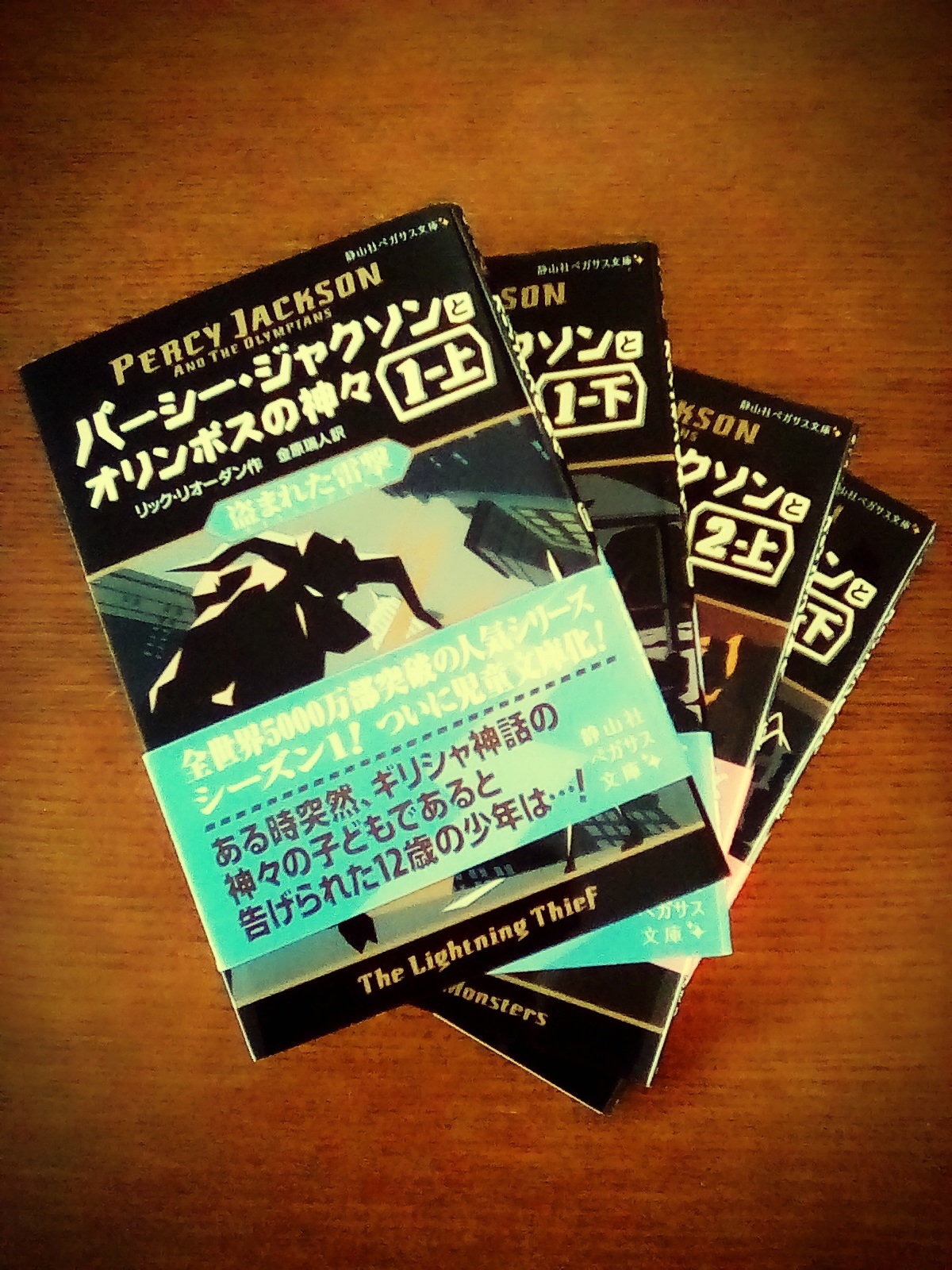
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d-600x600.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7acbbbd425e5b26784e40790cec66b8e-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/568915458f31e71b4cc0d2c9f85e8469-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8a9cc9d5e3e20eacab99f7a0fd74fe3f-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/a45e5bdd66128be187843fe1f35e8720-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/df16c82afd8de2b248066899a5b13034-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb77de07cae191366abcab605163c060.jpg)
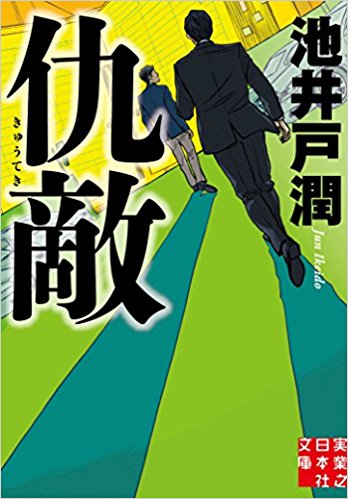
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/286239e57169f2e75c13f46a4ca87c43.jpg)
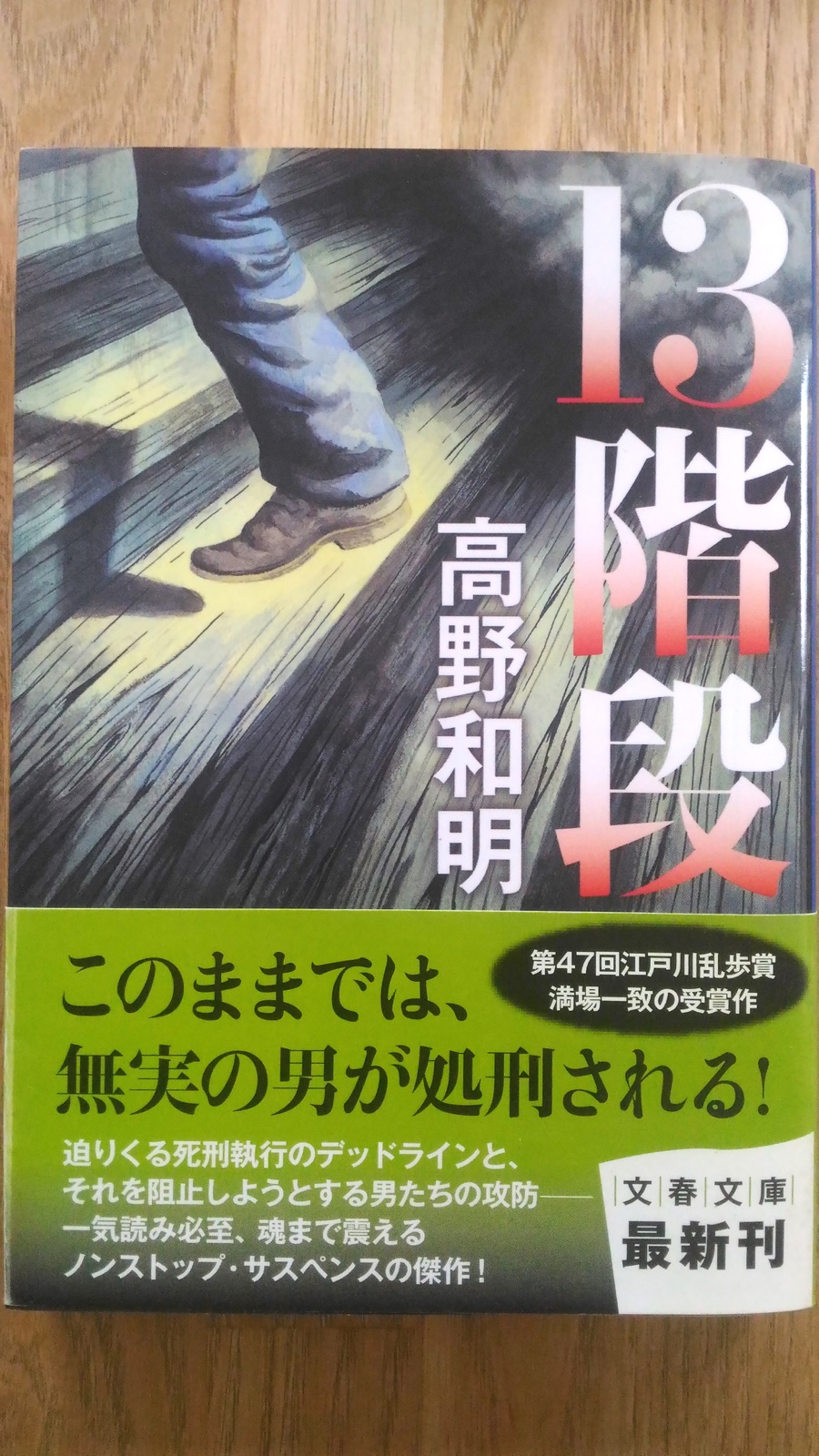
![小学館文庫 仙川環「感染」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4fcf537dcda4299d15e524ed1051a9f6.jpg)
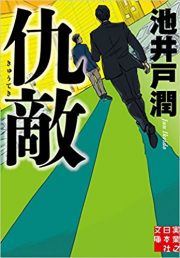
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d.jpg)