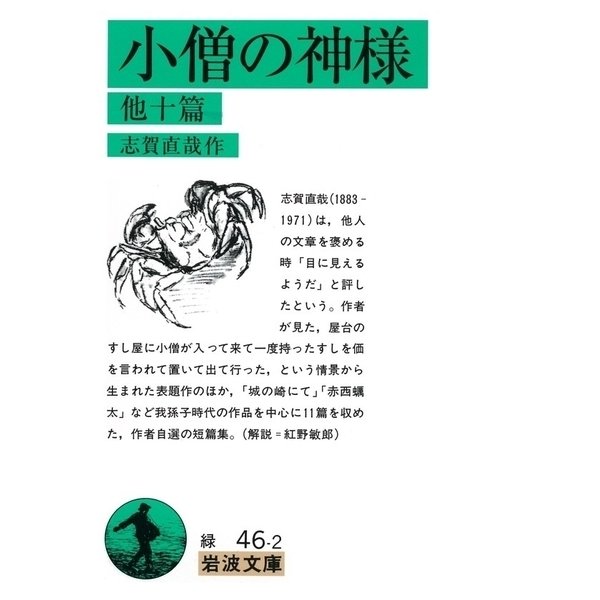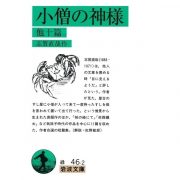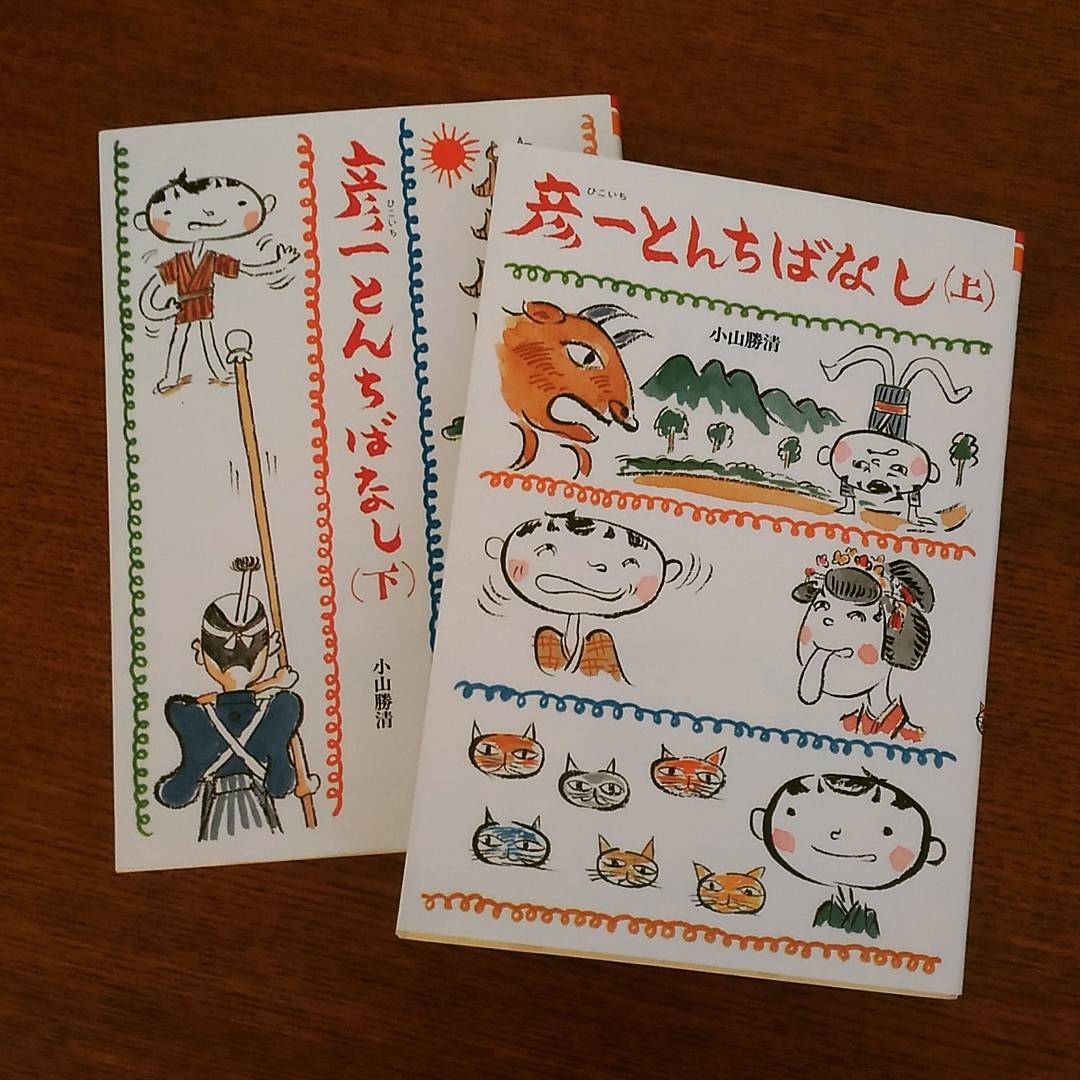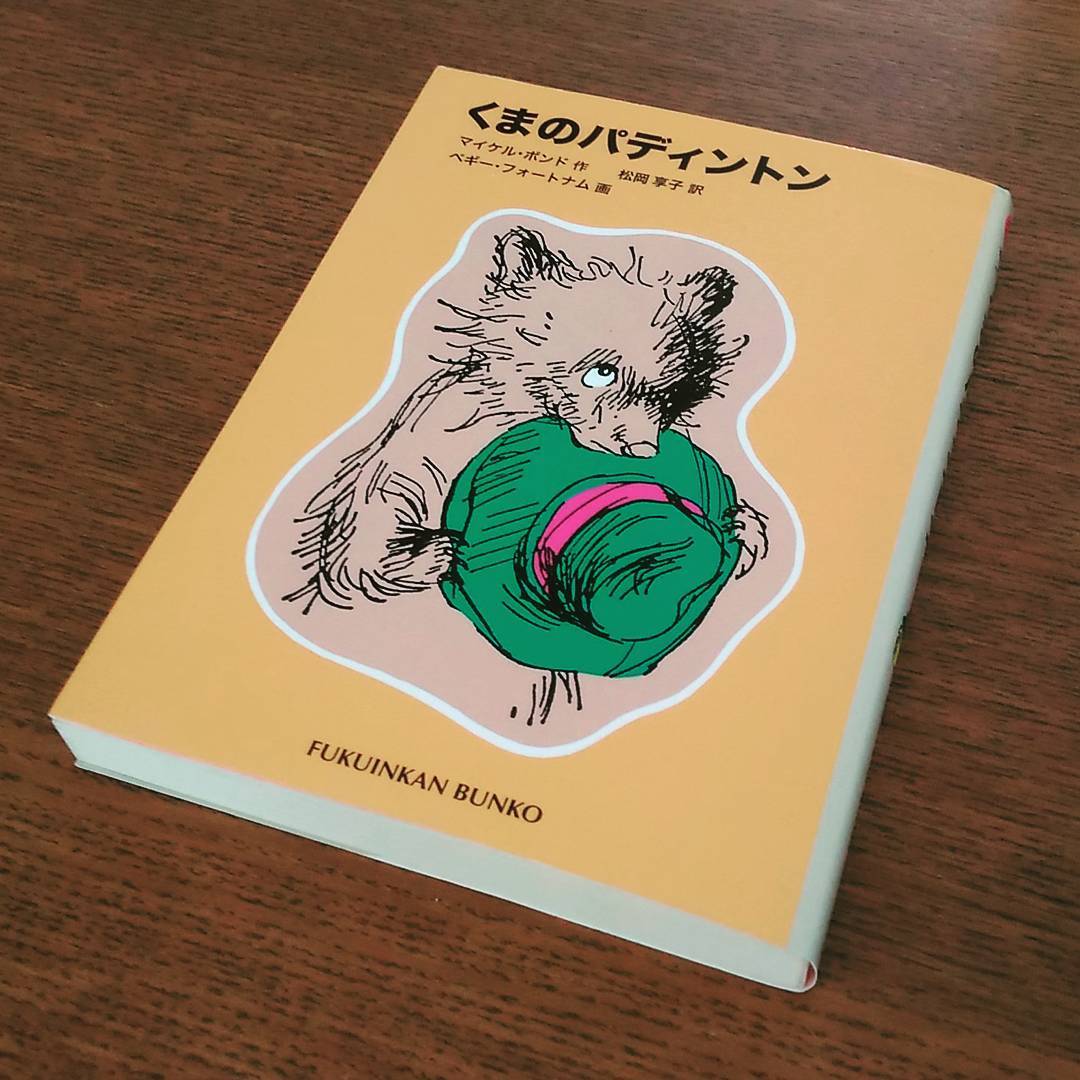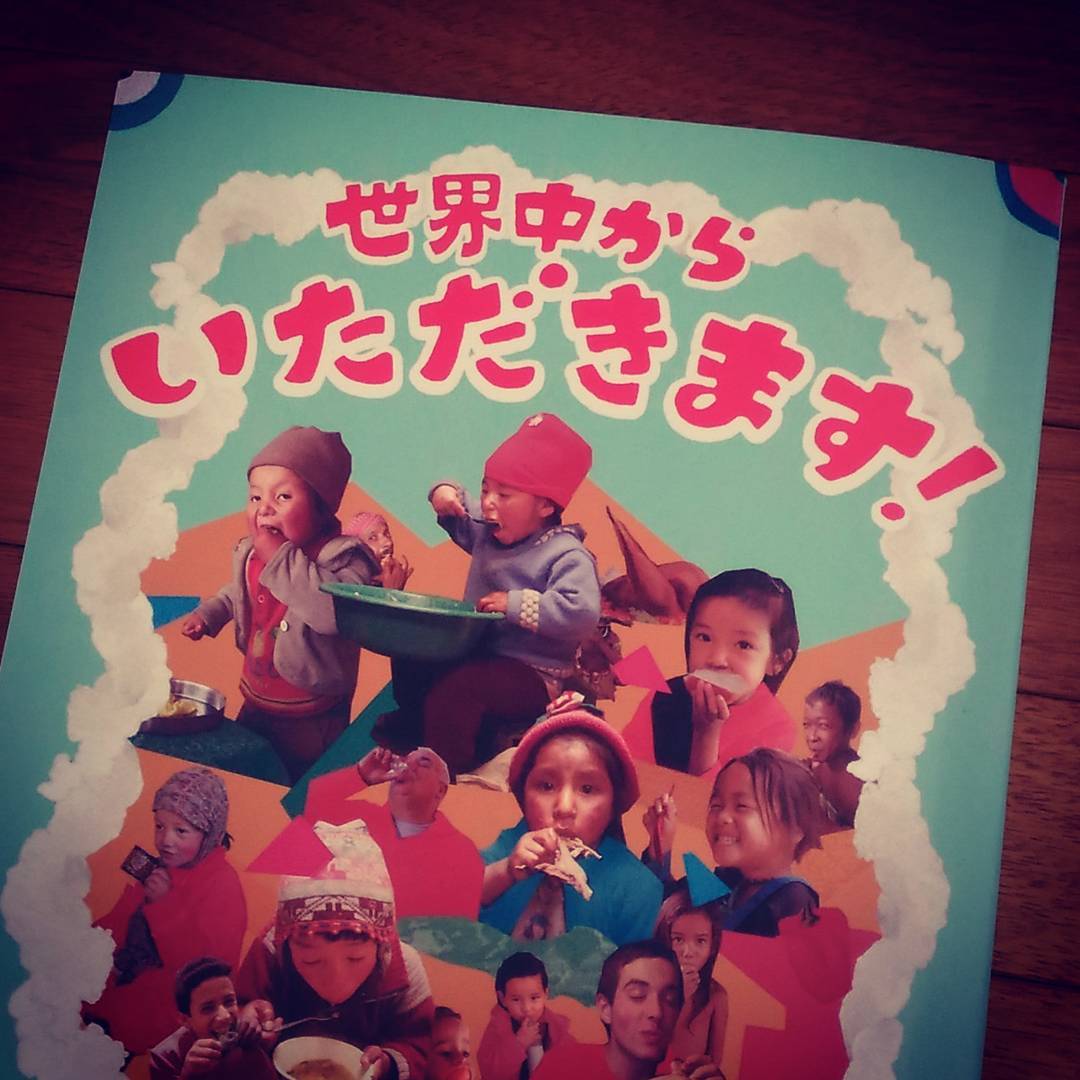【メモ】
・ともかく「読みやすい」の一言に尽きる文章。そして、非常にわかりやすく、面白い。シンプルに、ストレートに伝わってくる感じ。
・話の内容も、確かに現代の話では無いのは読んでいればわかるのだが、古臭さを感じさせられない。今この時代にも、神田や日本橋界隈には仙吉の働く秤屋があるのでは無いか、という気がしてしまう…。まさかこの本が今から85年(!)も前に出版された本とは。
【本文書き出し】
”小僧の神様 一
仙吉は神田のある秤屋の店に奉公している。
それは秋らしい柔らかな澄んだ日ざしが、紺のだいぶはげ落ちたのれんの下から静かに店先にさし込んでいる時だった。店には一人の客もない。帳場格子の中にすわって退屈そうに巻き煙草をふかしていた番頭が、火鉢のそばで新聞を読んでいる若い番頭にこんな風に話しかけた。
「おい、幸さん。そろそろお前の好きな鮪の脂身が食べられるころだネ」
「ええ」
「今夜あたりどうだね。お店をしまってから出かけるかネ」
「結構ですな」
「外濠に乗って行けば十五分だ」
「そうです」
「あの家のを食っちゃア、このへんのは食えないからネ」
「全くですよ」
若い番頭からは少しさがったしかるべき位置に、前掛けの下に両手を入れて、行儀よくすわっていた小僧の仙吉は、「ああすし屋の話だな」と思って聞いていた。京橋にSという同業の店がある。その店へ時々使いにやられるので、そのすし屋の位置だけはよく知っていた。仙吉は早く自分も番頭になって、そんな通らしい口をききながら、勝手にそういう家ののれんをくぐる身分になりたいものだと思った。
「なんでも、与兵衛のむすこが松屋の近所に店を出したという事だが、幸さん、お前は知らないかい」
「へえ存じませんな。松屋というとどこのです」
「私もよくは聞かなかったが、いずれ今川橋の松屋だろうよ」
「そうですか。で、そこはうまいんですか」
「そういう評判だ」
「やはり与兵衛ですか」
「いや、なんとかいった。何屋とかいったよ。聞いたが忘れた」
仙吉は「いろいろそういう名代の店があるものだな」と思って聞いていた、そして、
「しかしうまいというとぜんたいどういう具合にうまいのだろう」そう思いながら、口の中にたまって来る唾を、音のしないように用心しいしい飲み込んだ…”
【基本データ】
岩波文庫
1928年8月25日第一刷発行
志賀直哉「小僧の神様 他十篇」
ISBN4-00-310462-5
<!–
”この本、読ませてみたいな”と思ったら