【メモ】
・切なく、哀愁や郷愁を感じされられる短編集。どの話も、読後に心地よい感情が残る。
・短く区切られた、簡潔で読みやすい文章。極端ともいえるほどにシンプルな文体。すべてを書きすぎていないからこそ、読者は行間を読むことができる。読んだ人それぞれが、自らの経験や記憶にもとづいてイメージを脳内で補完し、ストーリーを完成させることができる。だからこそ切ない。だからこそ美しい、映画やテレビの映像、写実的に事細かに書き込まれた盛りだくさんの文書では、決して表現し得ないもの。
・感動。爽快、爽やか。記憶、追憶、切ない、郷愁。
・中学入試に採用されるというのもうなずける。そのために読むんじゃないけれど、そのために読む必要もないけれど、小学生の息子にも読ませてみたい。まあ、経験がなさすぎて、なんだかちんぷんかんぷん、この本の良さはまだわからないかもだけど。
・中でも僕の一番のおすすめは、「バスに乗って」。小学生でも十分に理解できる、愛情に満ちあふれた、心温まるショートストーリー。下手な読解力トレーニング用のテキストなんかをやらせるより、この一話をしっかりと読ませるほうが、いろいろな意味で100倍子どものためになると思う。「おとうと」もいいです。友人との話もいいけれど、やはり、親子や兄弟、家族がお互いを思いやる気持ちやその愛情を描いたストーリーが素敵。
※男女の体の発達や第二次性徴など、小学校高学年以上向けかもと思われるような話や表現が一部に出てきますので、小学生以下のお子さんに読ませる際には、保護者の方が確認された上で判断されることをおすすめします。個人的には、小学生であっても読ませても大丈夫な範囲に収まっているのではないかと思います。
【本文書き出し】
” この町に引っ越してきて初めてデパートに出かけた日曜日、少年はお母さんに写真立てを買ってもらった。二枚合せになった透明なアクリル板にしいさなスタンドがついただけの、簡単な写真立てだった。文具売り場の棚にはフレームが飾り付いたものやペン立てとセットになったものもあったが、「どれにする?」とお母さんに訊かれたとき、いちばんシンプルなものを指差した—それがいちばんオトナっぽくて、オトコっぽいと思ったから。
家に帰ると、さっそくアクリル板に写真を挟んだ。昨日手紙と一緒に届いたばかりの写真だ。三人の男の子が、花が咲いた桜の木をバックに並んで立っている。少年を真ん中に、向かって右がエンドウくんで、左がヒノくん。三人ともカメラに向かってVサインをつくり、にっこり笑っている。四年生の終業式の日に撮った写真のうちの一枚だった。カメラの持ち主のハラくんは、他にも数枚の写真を焼き増しして送ってくれた。エンドウくんやヒノくんよりも仲良しだった子と一緒の写真もあったが、写真立てに入れるのは、この写真でなくてはいけない。
三人が背にした桜の木は、町の中でもいちばん大きな木だった。三人がかりで手をつないでも一周できないほどの太い幹の反対側で、女子が記念撮影をしていた。少年と同じように終業式を最後に転校してしまう子が、女子にもいた。ユキコという。背が高くて、足が速くて、おとなしいけれどリコーダーのとても上手な子。
写真立てに入れた一枚には、ユキコが写っている。たまたまだった。女子の撮影が先に終わって、幹の向こう側からひょいと顔をだした、ちょうどどのときハラくんがシャッターを切ったのだ。カメラを見ていた。笑顔がすぼむ直前の、ぎりぎりのところで、笑っていた。
だから—この写真、なのだ。
傷も汚れもついていないアクリル板を隔てて見つめるユキコの顔は、写真をじかに見るときよりも光沢が増してきれいだった……”
【表紙及び冒頭5ページ】
【子どもの読書に関わるデータ】
ふりがなの状況:ほぼなし(難読のもののみ、ごくまれにふりがなが振られています)
文字の大きさ:小さい、大人向け文庫とほぼ同等サイズ
所感:子ども向けに書かれた本というわけではありませんが、平易な読みやすい文書で書かれており、内容的にも、小学校高学年程度であれば十分に読むことができます。また、親として、「小学校高学年〜中学入学程度の時期に読ませてみたい(かも)」と思わさせられる内容でもあると感じました(重松清氏の小説は中学入試問題に使用されることも多いとのことで、そういった意味でも、小学校高学年のお子さんに読ませてみるというのはありだと思います)。
【基本データ】
文春文庫
2009年12月10日第一刷
重松清「小学五年生」
ISBN978-4-16-766908-9
”この本、読ませてみたいな”と思ったら
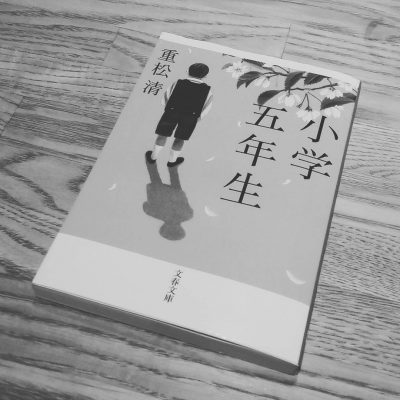
![重松清 小学五年生 文春文庫 表表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/d6a6ed3f1ba62e2f520fa62de16fa8e5-180x320.jpg)
![重松清 小学五年生 文春文庫1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/aa743dfd784c2710f69c97482c40edca-180x320.jpg)
![重松清 小学五年生 文春文庫 本文1_[1]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/16f36f728698c2297b4fe2c2765babbd-180x320.jpg)
![重松清 小学五年生 文春文庫 本文2_[1]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4a5af83127c50ac25bcdd7bd4d9fc6e9-180x320.jpg)
![重松清 小学五年生 文春文庫 本文3_[1]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/d53bfa328960c79fc35bf770f3e25fb3-180x320.jpg)
![重松清 小学五年生 文春文庫 本文4_[1]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e0c378898b018e21ad5441a7ed1429ef-180x320.jpg)
![文春文庫 横山秀夫「クライマーズ・ハイ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/3166db91771b097363cd384cce52758f.jpg)
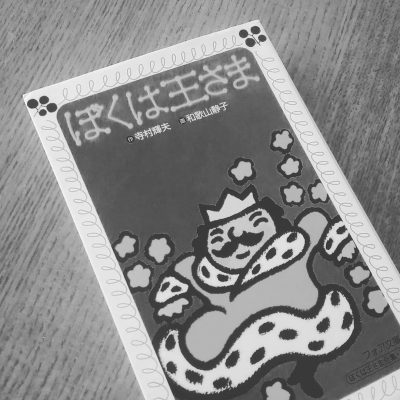
![フォア文庫「ぼくは王さま」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/bd28b1caad44decad6115e09c0b8f9de-180x320.jpg)
![フォア文庫「ぼくは王さま」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/987d664bec73a35a69d896369b0c6c1e-180x320.jpg)
![フォア文庫「ぼくは王さま」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/f4cb81aecf2e2cf66d58437c37b17daf-180x320.jpg)
![フォア文庫「ぼくは王さま」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/d09ad42e988fe1a6f7264f28a95d45c3-180x320.jpg)
![フォア文庫「ぼくは王さま」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6798fdfadd92571da3b8ee14872cc9bc-180x320.jpg)
![フォア文庫「ぼくは王さま」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/d0a3dc477c7133c495624f28c2ba14d1-180x320.jpg)

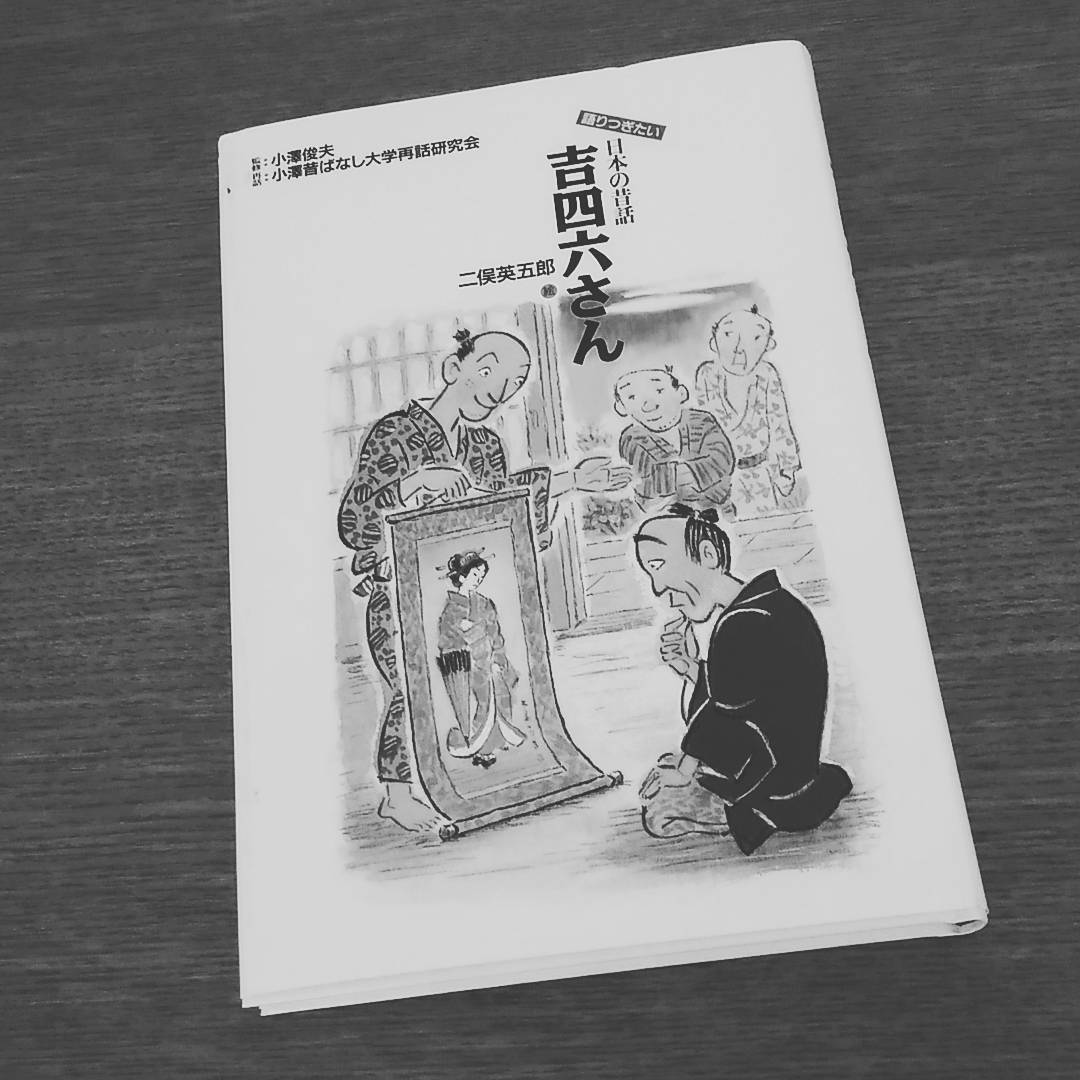
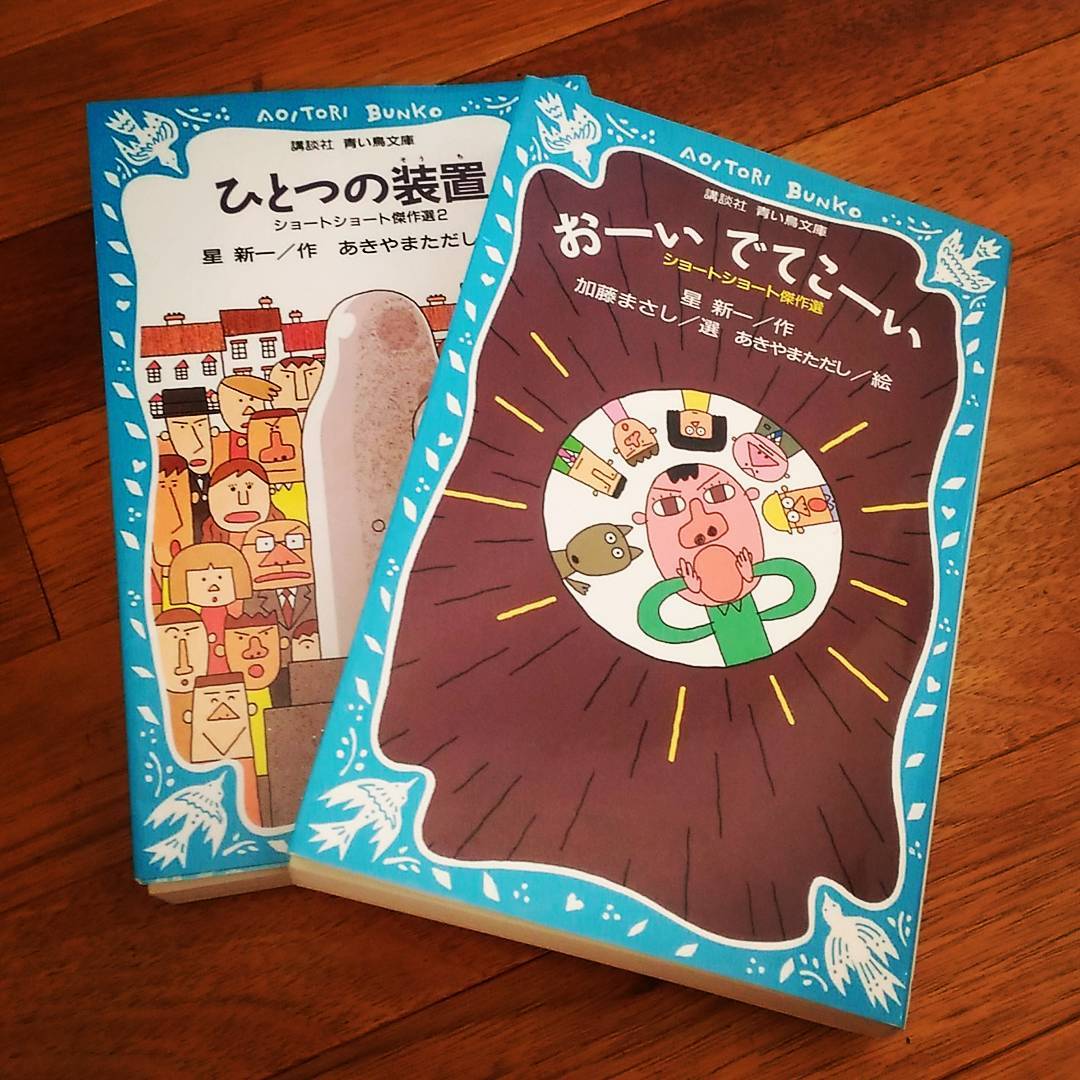
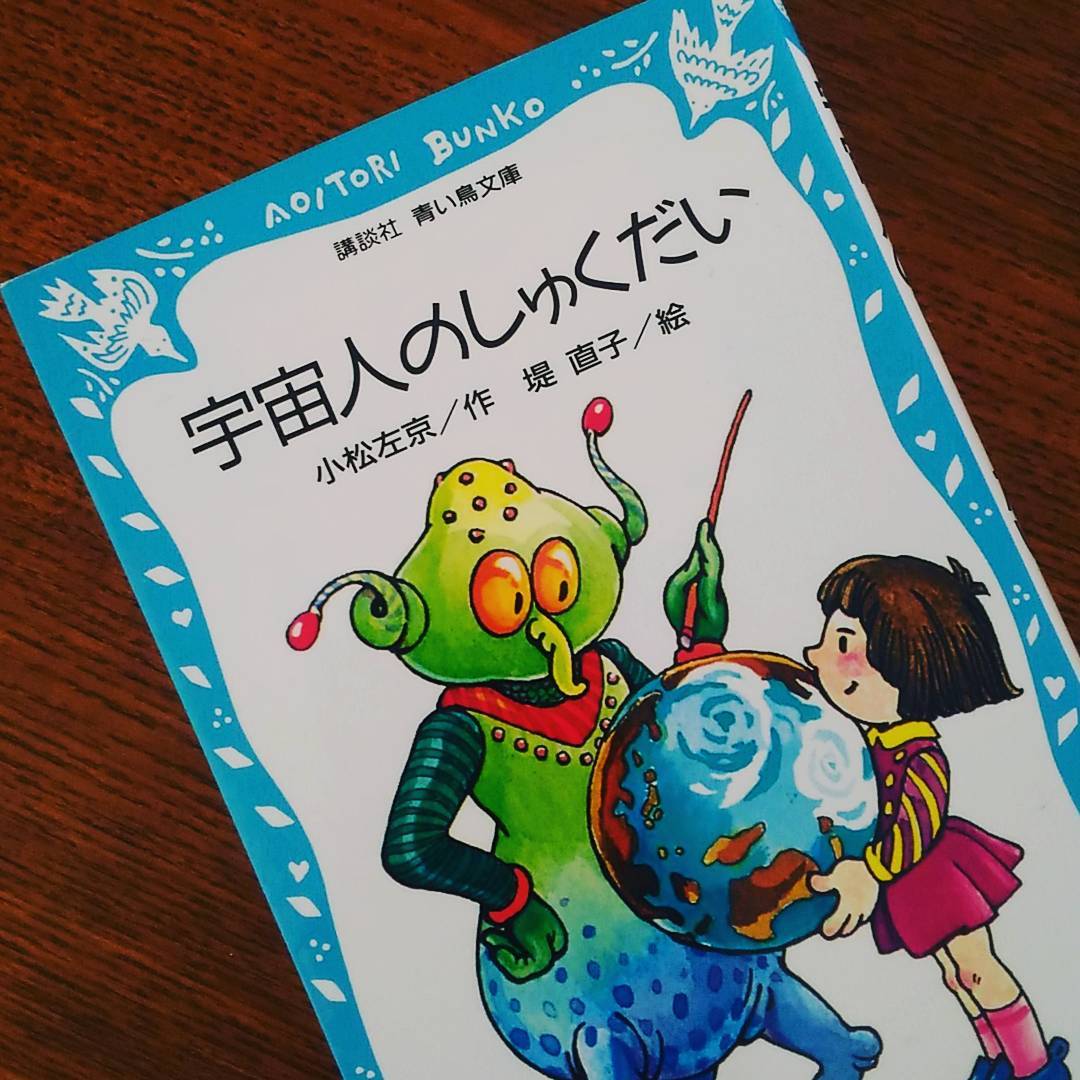
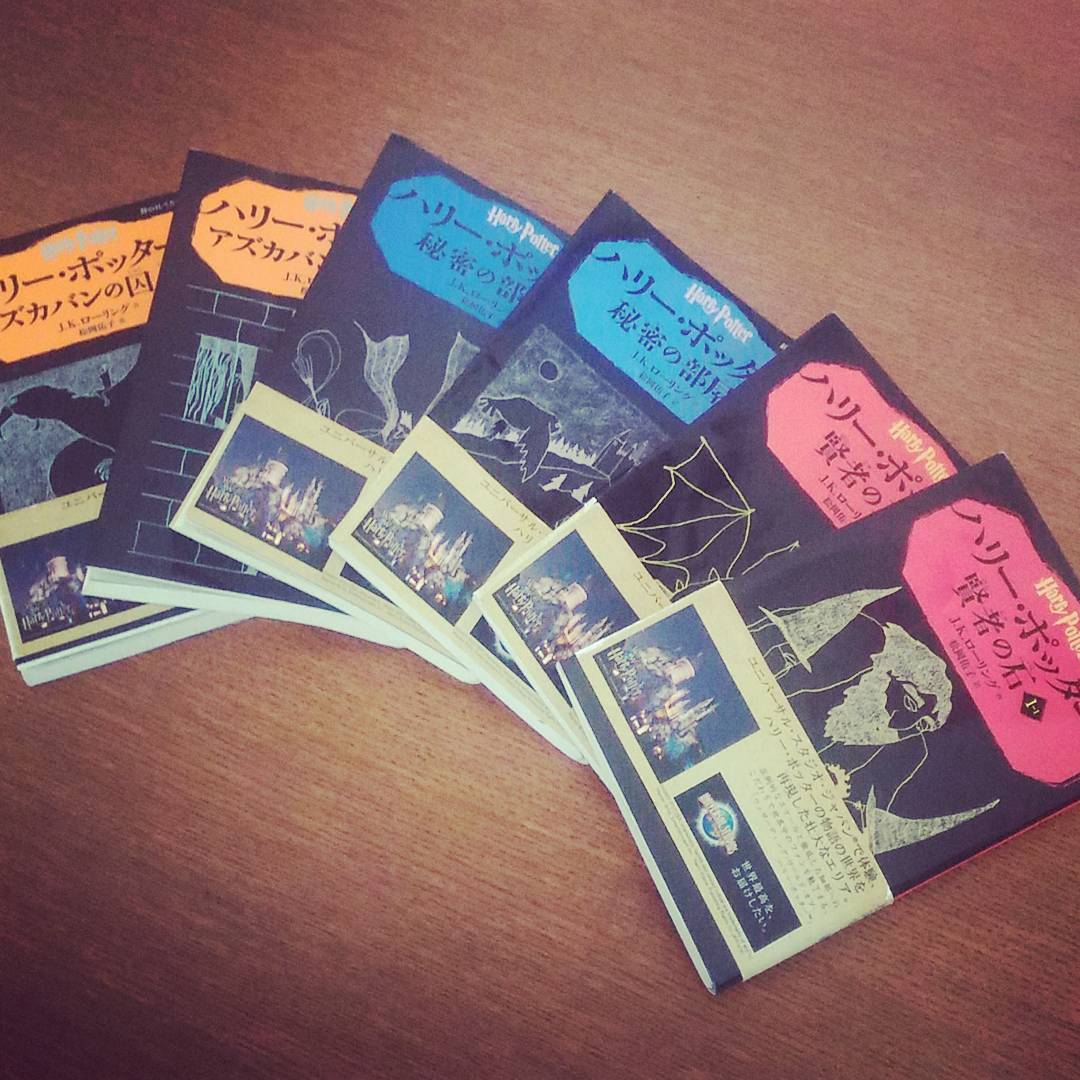
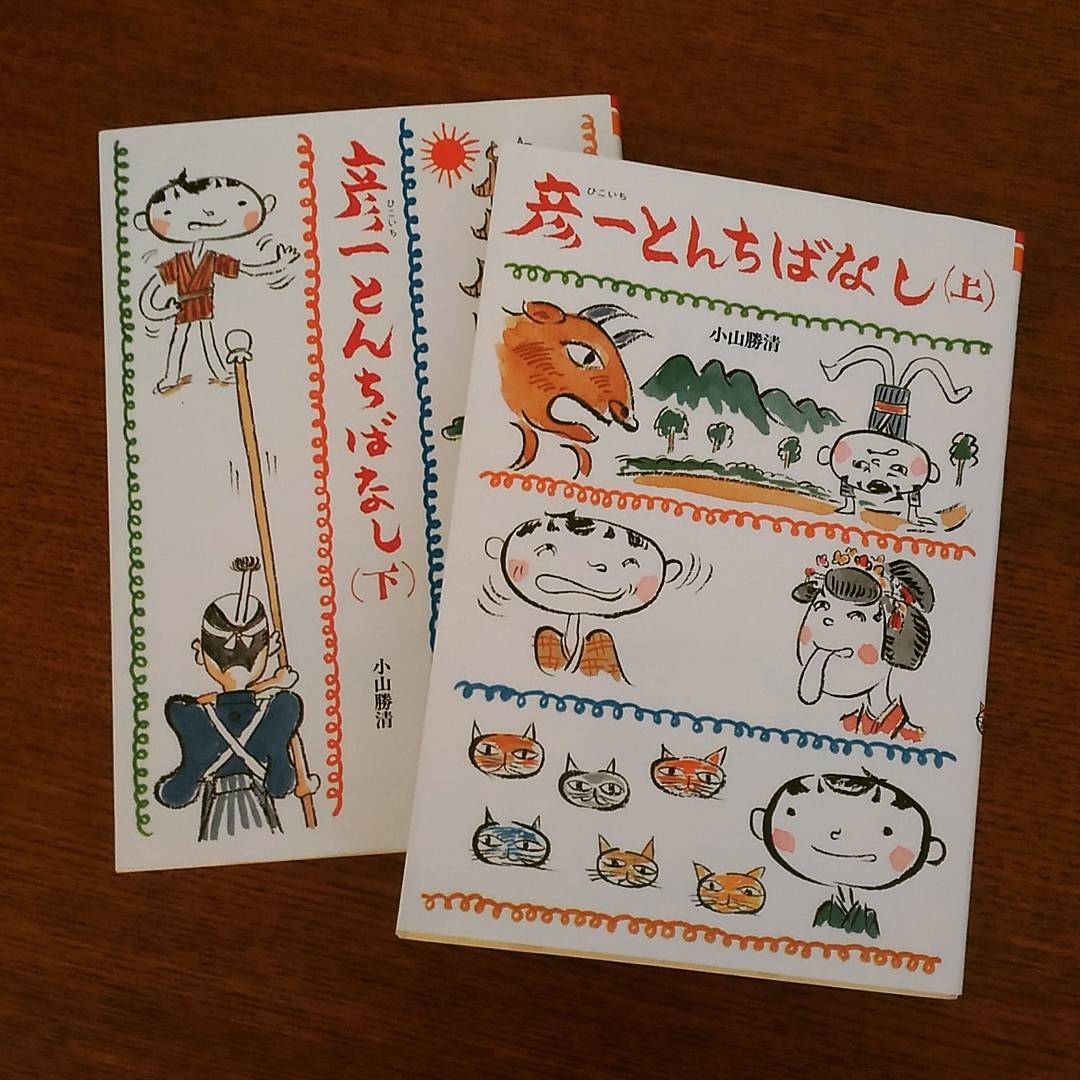
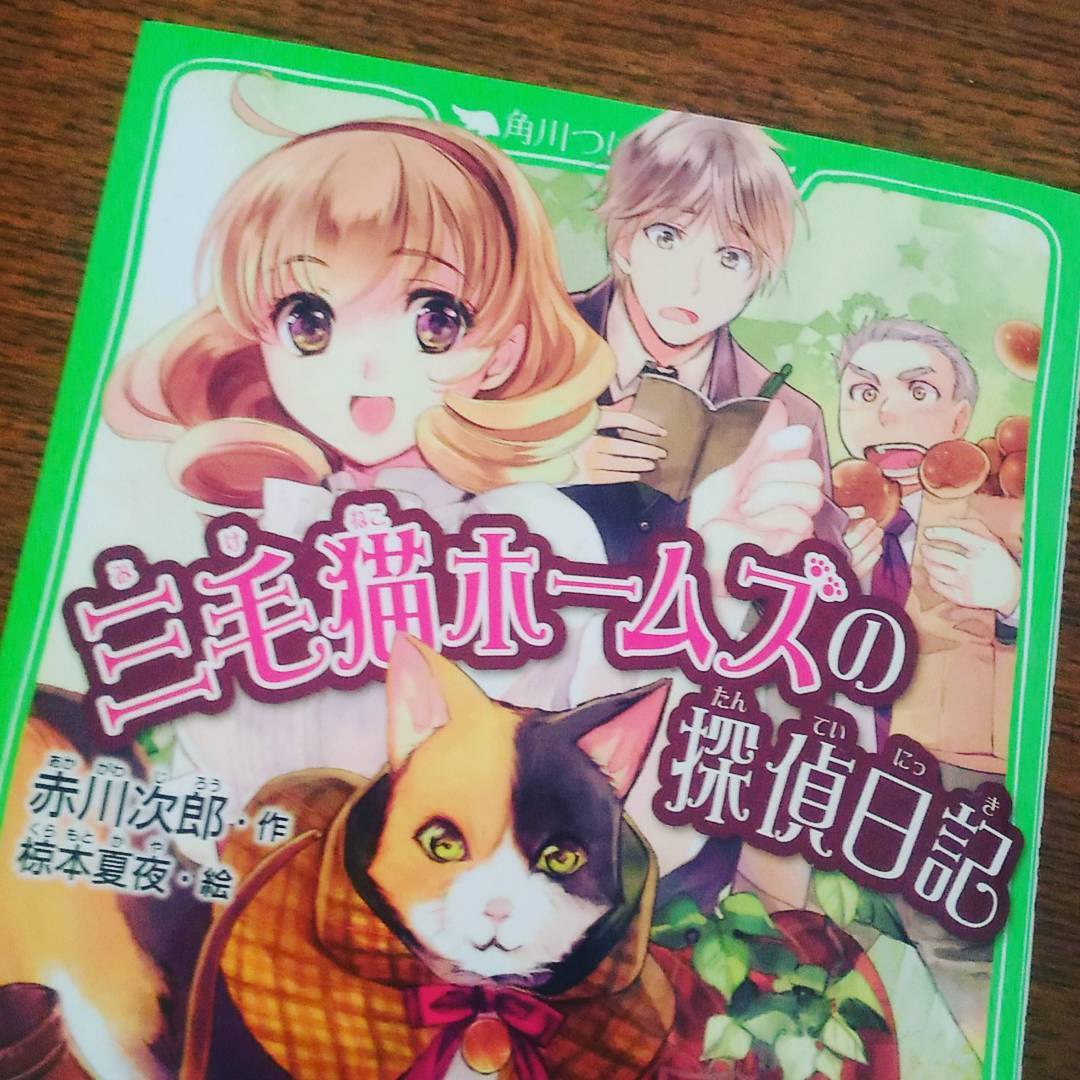
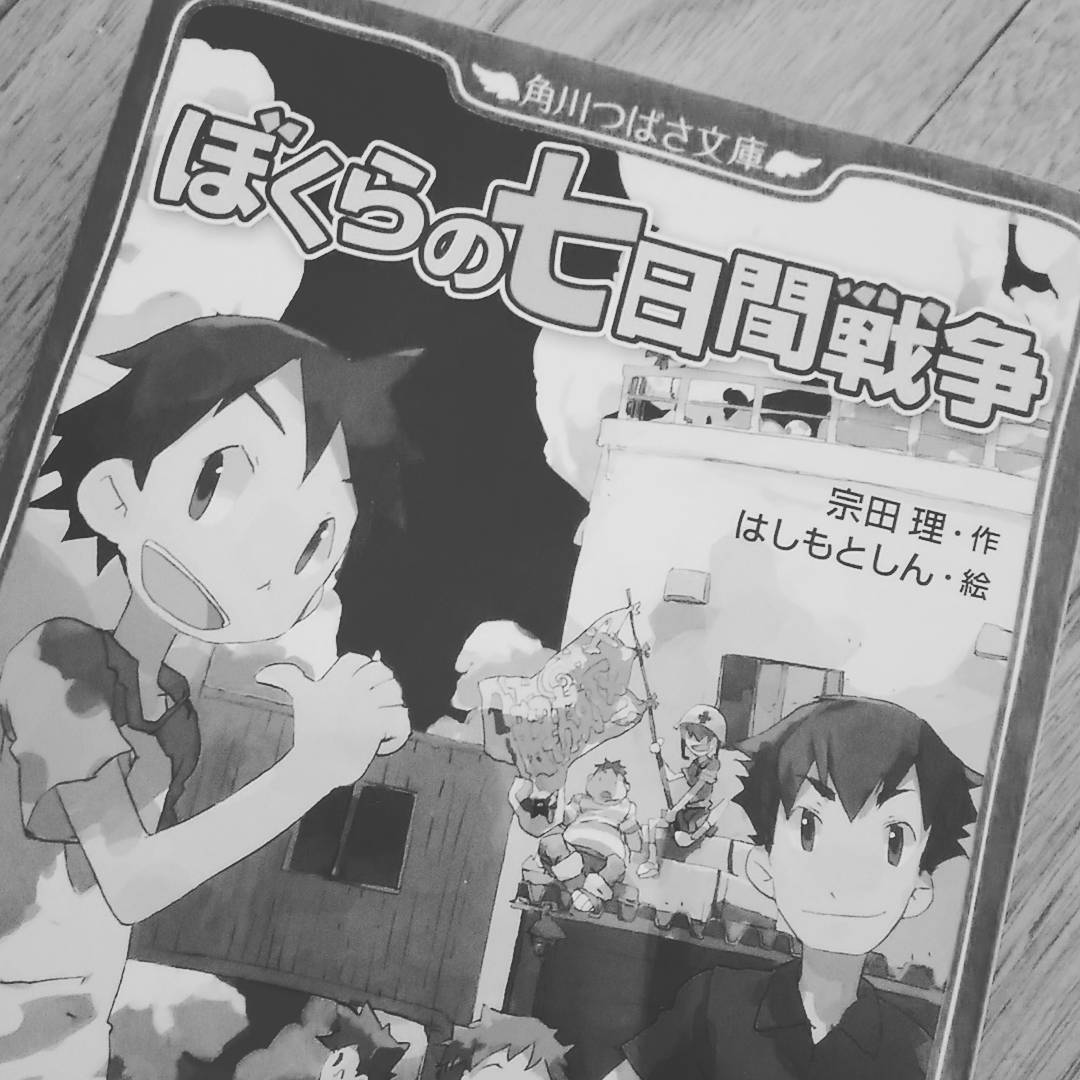
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c14ae0c0ef02b71aa20abe673d6690bb-600x600.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c14ae0c0ef02b71aa20abe673d6690bb-180x320.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/5a7ece8eddcdf267128d4dfccdc94d51-180x320.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e23de38187b81fcb3bd322ba669bcbca-180x320.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8c398ebc26d055e3b67d00e1540a697d-180x320.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/dca2c0e9917730a1799db2a146a8817f-180x320.jpg)
![文春文庫 安野モヨコ「くいいじ」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/b29fba84311b5e139bead7950cb8a08d-180x320.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「池波正太郎の銀座日記〔全〕」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/46c46d71e87638fc9705d221dc608dd7.jpg)
![新潮文庫 池波正太郎「男の作法」1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/26842a450d4c17ddcbdb3de87254bdbf.jpg)