【メモ】
・子供の臓器移植とそれを取り巻く親、周囲。
・異なる種のもつウイルス。
・こう言った話が現実世界の話とどの位リンクしているものなのか知らないので、なんとも言えないところもあるけれど、切り口、ストーリの展開、描き方はとても面白いと思った。
・「物事をクローズアップすると”悲劇”」。現場の人は、常に何かと戦っている。そういったストーリを読むのが好きな人にはオススメの話か。
【書き出し】
”1
手術室を出ると、仲沢啓介は大きく息を吐き出した。肩をぐるりと二度ばかりまわしてみる。首の後ろが熱を帯びていて熱い。難しい手術の後、決まってそこが熱くなる。
患者を乗せたストレッチャーを押した看護師が、廊下の端にあるエレベーターに乗り込むところだった。
水色のキャップを脱ぐと丸めてポケットに押し込んだ。廊下を照らす蛍光灯がまぶしくて、啓介は目を細めた。
「先生!」
背後から声をかけられた。スーツ姿の小柄な男が深々と頭を下げている。
「ありがとうございます。なんとお礼を申し上げればいいのか。社長にもしものことがあったら我が社は・・・・・・」
男は顔をあげると、目元をひくひくとふるわせた。
さっき心臓のバイパス手術をした患者は社員五十人ほどの精密部品メーカーの創業者だった。目の前にいる男は、番頭役の専務あたりだろうと見当をつける。
「あの、これほんのわずかですが」
男が上着の内ポケットから白い封筒を取り出した。厚みを目で確認する。
「気を遣っていただかなくても結構です」
啓介が言うと、男は首を左右に振り、啓介の手に封筒を押し付けた。予想したとおりの行動だった。
「そうおっしゃらずに」
啓介はうなずいた。
「それでは遠慮無く」
男は安堵したように何度も頭を下げた。啓介は封筒をズボンのポケットに入れた。
「仲沢先生!」
シャワー室の手前で看護師に呼び止められて、啓介は足を止めた。
「謝礼を受け取るのは禁止されているじゃありませんか」
看護師はカルテを胸に抱えたまま、よく光る目で啓介を見上げた。
「どうしちゃったんですか?昔は先生、そんな人じゃなかったのに」
啓介は苦笑いを浮かべた。そういえばそんな頃もあった。が、今は綺麗ごとを言っていられる場合ではない。金はあればあるほどありがたい。啓介は看護師から目を逸らして言った。
「学部長の岸川先生に言いつけてみたらどうだ?どうせ無駄だとは思うがね。ほかのドクターだって同じようなことをしているんだから」
看護師の頬がさっと紅潮した。猫のような目で啓介をにらみつけてくる。啓介は首の後ろを手で揉むと、シャワー室の扉を押した。
2
洗面台の鏡に映った自分と目を合わせる。何かに怯えたような目。不安げな表情が自分でも嫌になる。平凡な顔立ちだということは、自覚している。それでも昔は、表情から意志の強さを読み取ることができた。今、鏡の中を探してもそんな自分はどこにもいない。
仲沢葉月はため息をつくと、化粧水の瓶を手に取り、とろりとした液体をコットンにしみこませた。
丁寧に頬をぬぐう。目元にも化粧水を叩き込む。リズミカルに手を動かしているうちに、涙がにじんできた。
啓介は何故、自分と結婚したのだろう。今さらながらそう思う。結婚を自分から口にしたことはない。そんなことができるはずもなかった。啓介には妻と三歳の子供がいた。
リビングルームのソファに座ると葉月は煙草に火をつけた。啓介と結婚する前のことを思い返す。仲沢啓介という外科医の名は、東都大学に来る前から知っていた。アメリカで臓器移植を手がけていたこともある高名な医師の名は、医学雑誌だけでなく新聞にも取り上げられていた。その彼がウイルス研究を専門としている葉月に教えを請いに来たときには驚いたが、話を聞いて納得した。移植後の患者は免疫抑制剤を服用するから、様々な感染症の危険にさらされる。最新の知識を得たいといって、週に一度ほど夜の比較的暇な時間、啓介は葉月のところに話をしにくるようになった…”
【表紙及び冒頭5ページ】
【基本データ】
小学館文庫
二〇〇五年九月一日 初版第一刷発行
仙川環「感染」
ISBN4-09-408046-5
”この本、読ませてみたいな”と思ったら
![小学館文庫 仙川環「感染」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4fcf537dcda4299d15e524ed1051a9f6-600x600.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4fcf537dcda4299d15e524ed1051a9f6-180x320.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/d0478d8d9a226ab83e0366634e318d68-180x320.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0fcf888e4f82ac3594fff2cee5af6a36-180x320.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/5e220257817f3ce711445d639d6478fb-180x320.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4527782bf46aecedb4f58b87962a720c-180x320.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/63e8303e14737a2f3ccc2b8d55b38965-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb77de07cae191366abcab605163c060.jpg)
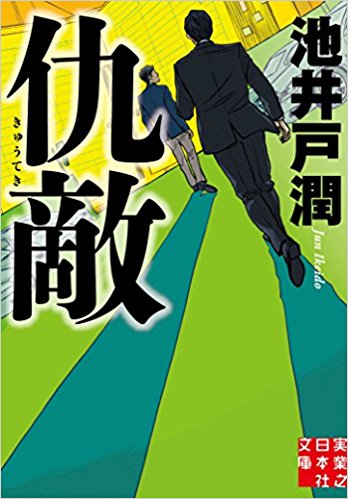
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d.jpg)