【メモ】
・菊池直子、高橋克也、両容疑者が逮捕されたからといって読み返したわけではないんですが、改めて読んでみても、当時の関係者の方々の「見たもの」を忠実に記録として残そうという著者の取り組みは素晴らしいものであったと思います。
・事件発生当時、僕は大学3年生。留年が確定していたため就職活動はしていなかったけれど、まわりには、就職活動のために霞が関近辺に行っていたり、サリンの置かれた電車と「ニアミス」をした友人もいました。実家の最寄り駅も、千代田線の大手町から数駅の駅であり、今考えてみても、地下鉄サリン事件は「すぐそこ」で起きたテロ事件だったと思います。
・にもかかわらず、この事件がどこか「別の世界」で起きている事件のようにしか思えなかった記憶があります。それが何故なのか、実際に「地下鉄サリン事件」とはどんな事件だったのか、それを改めて考えてみたくて、この本を手にしました。
・「アンダーグラウンド」を読みながら不思議なことを感じました。それは、地下鉄サリン事件という事件のもつ「非現実感」です。著者村上春樹氏の中にも、そして、実際に事件の被害に遭われた方々の中にも、そして、この本を通じて描かれている日本という社会全体にも、僕が感じたような「非現実感」が漂っていた(今でも漂っている)のではないか、ということでした。
・それは村上春樹氏が、「忠実な記録」を作成しようとしたからこそ文章の中に再現することができた、「地下鉄サリン事件(及び、その事件が発生した日本という国、その社会)」の真実なのかもしれません。
・全ての指名手配犯が逮捕されたこのタイミングを一つの区切りとして、再び村上春樹氏に何かを書いてみて欲しい気がします。
【本文書き出しより】
”「はじめに」
ある日の午後、たまたまテーブルの上にあったその雑誌を手に取り、ぱらぱらとページを繰ってみた。いくつかの記事を流し読みし、それから投書欄に掲載されていた読者の手紙にひとつひとつ目を通してみた。どうしてそんなことをしたのか、よく思い出せない。たぶんちょっとした気まぐれだったのだろう。あるいはよほど暇だったのかもしれない。女性誌を手に取ることも、また投書欄を読むことも、私にとってはけっこう珍しいことだから。
手紙は、地下鉄サリン事件のために職を失った夫を持つ、一人の女性によって書かれていた。彼女の夫は会社に通勤している途中で運悪くサリン事件に遭遇した。倒れて病院に運び込まれ、数日後に退院はできたものの、不幸にも後遺症が残り、思うように仕事をすることができなくなった。最初のうちはまだ良かったのだけれど、事件後時間が経つと、上司や同僚がちくちくと嫌みを言うようになった。夫はそのような冷たい環境に耐えきれずに、ほとんど追い出されるようなかっこうで仕事を辞めた。
雑誌がいま手元に見つからないので、正確な文章までは思い出せないけれど、だいたいそういう内容だったと思う。
記憶している限りでは、それほど「切々とした」文面ではなかった。またとくに怒っているというのでもなかった。どちらかといえば物静かで、むしろ「愚痴っぽい」ほうに近かったかもしれない。「いったいどうしてこんなことになってしまったのかしら・・・・・・?」と戸惑っているような感じもあった。運命の急激な変転がいまだうまくのみこめずに、首をひねっているような。
手紙を読んで私はびっくりしてしまった。
どうしてそんなことが起こるのだろう?
その夫婦が負った心の傷は、言うまでもなく、深く厳しいものであったに違いない。「ほんとうに気の毒に」と心から思った。でもそれがご本人にとって、「気の毒に」というだけではとてもすませられない出来事であることもよくわかっていた。
しかしだからといって、今ここで自分に何かができるわけでもない。私は—たぶん多くの方がそうなさるであろうように—溜息をついて雑誌のページを閉じ、自分自身のいつもの生活と仕事の中に戻っていった。
でもそのあと、何かにつけてその手紙のことを思い出した。「どうして?」という疑問は私の頭から去らなかった。それはとても大きなクエスチョンマークだった。
不幸にもサリン事件に遭遇した純粋な「被害者」が、事件そのものによる痛みだけでは足りず、何故そのような酷い「二次災害」まで(それは言い換えれば、私たちのまわりのどこにでもある平常な社会が生み出す暴力だ)受けなくてはならないのか?まわりの誰にもそれを止めることはできなかったのか?
そして、やがてこうも思うようにもなった。
その気の毒な若いサラリーマンが受けた二重の激しい暴力を、はたの人が「ほら、こっちは異常な世界から来たものですよ」「ほら、こっちは正常な世界から来たものですよ」と理論づけて分別して見せたところで、当事者にとっては、それは何の説得力も持たないんじゃないか、と。その二種類の暴力をあっちとこっちとに分別して考えることなんて、彼にとってはたぶん不可能だろう。考えれば考えるほど、それらは目に見えるかたちこそ違え、同じ地下の根っこから生えてきている同質のものであるように思えてくる。
私はその手紙を書いてきた女性(たち)のことを知りたいと思うようになった。その夫(たち)のことを知りたいと思うようになった。個人的に。そしてかくのごとき二重の激しい傷を生み出す我々の社会の成り立ちについて、より深く事実を知りたいと思うようになった。
地下鉄サリン事件の被害者のインタビューをやってみようを具体的に決心したのは、その少しあとのことである。
もちろんその投書の手紙だけが、本書を書いた唯一の理由ではない。それは現実的な点火プラグのようなものだった。その時点で私の中には、この本を書くべきいくつかの大きな、個人的な動機が既に存在していたのだ。しかしそれについては最後の部分でゆっくりと語りたいと思う。とりあえずは本を読んでみていただきたい…”
”千代田線 A725K
地下鉄千代田線のサリン散布の実行チームは、林郁夫と新實智光の組み合わせだった。林が実行犯、新實が運転手役である。年長者であり医師であり、科学技術省の「武闘派」とは一線を画している林が敢えて実行者として選ばれた理由は不明だが、「おそらくは口封じのためだろう」と林自身は推測している。事件に関与させることによって、逃げ道を断つわけだ。この時点で既に、林は知りすぎた男だった。林は麻原彰晃に深く帰依していたが、麻原の方は心の底からはこの男を信用していなかったらしい。「サリンを撒け」と言われたときには、「胸の中で心臓が縮みあがるような思いがした」と本人は語る。「心臓が胸の中にあるのは当然のことですが」と断りながら…”
”「一目見たとき、冷静にことを処理している人が一人もいないことに気がつきました」
和泉きよか 当時二六歳
和泉さんは金沢生まれ。現在は外資系航空会社の広報課に勤務している。
大学卒業後いろんな事情でJRに総合職として入ったが、三年間そこで仕事をしたあと、どうしても航空関係の仕事がしたくなって、二年前に思い切って転職した。航空会社に入ることは、子供の時からの夢だったのだ。しかしこの航空会社に中途入社するには、一〇〇〇人に一人というすごい難関を突破しなくてはならなかったということだ。そしてこの転職直後の時期に、通勤途中でサリン事件に遭遇したわけである…”
”事件のあったことは早稲田に住んでいたんです。狭くなったので、最近引っ越したんですが。
会社は神谷町にあったので、私は東西線で早稲田から乗りまして、大手町で降りて、千代田線で霞が関、そこで乗り換えて日比谷線で神谷町まで一駅というルートで通っていました。会社が始まるのが八時半ですから、家はだいたい七時四五分か五〇分くらいに出ます。会社には八時半少し前に着くわけですが、それでも私は出勤の早いほうなんですよ。みんなもっとぎりぎりの時間に出てきます。日本の会社では始業時間の三〇分あるいは一時間前に出てきて当たり前という風に教育されるんですが、外資系はめいめい好きなペースで仕事を始めるという考え方です。始業時間より早く出てきたからといって、評価の対象にはなりません。
朝起きるのは六時一五分か二〇分くらいです。朝食はあまり食べません。軽くコーヒーを飲むくらいですね。東西線の電車はかなり混みますが、混むことを別にすれば、特に不快なことはありません。これまでのところ痴漢にあったようなこともありませんね。
私は普段、体の具合が悪くなるというようなことはほとんどない人なんですが、その三月二〇日はあさから体調が悪かったんです。ものすごく悪かった。でも出勤しようと電車に乗って、東西線を降りて大手町で千代田線に乗り換えて、「今日は調子良くないなあ」って思いながら、何気なくふうっと息を吸い込んだら、そのままいきなり息が止まってしまったんです。
そのとき私は千代田線のいちばん前の車両に乗っていました。そうすると霞が関駅に着いたときに、日比谷線の乗り換え口に一番近いんです。電車はそんなに混んではいませんでしたね。座席はいちおう全部埋まっていましたが、立っている人はぱらぱらという感じでした。向こうまで見渡せるくらいのものです…”
【表紙及び本文8ページ】
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/067c6a3a4eec09284c3afbd457da3bbe-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/804f5d050261b3666ea423de338ca4ff-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6a8bbd8f583af56b77e9067586fbf43c-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4729eb5e39691648aef5d182771438df-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8f174248b8331a4cf720739f7a44b3f3-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb79c321d57027ddc1cafcda86a6c73d-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文6_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/fbbb9bdc315ed949ad05d00c5bd1e35d-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文7_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6b56a6954ba99077b6ffe2af75e46d08-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文8_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/432cdfcc2ca742d146f944d940cbeda6-180x320.jpg)
【基本データ】
講談社文庫
1999年2月15日初版発行
村上春樹「アンダーグラウンド」
ISBN4-06-263997-1
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb77de07cae191366abcab605163c060-600x600.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb77de07cae191366abcab605163c060-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/cb979c04b4386056b4c04d84dad446e4-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/a7f3ef1455ed804eb6b9c41f7b50f1e3-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/35d1456f6d6097b5f98923b981987ee2-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7e30c3d4349ae2cd9c7e204fea84a2f7-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e1927d656745c67c36d5fa84457ce205-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d.jpg)
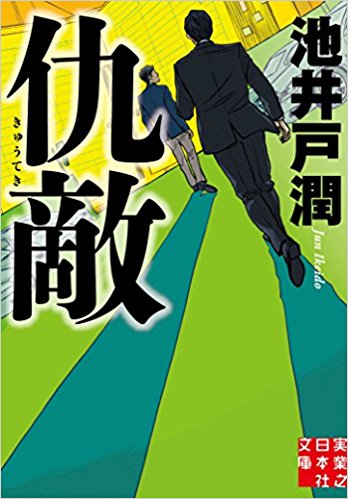
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/286239e57169f2e75c13f46a4ca87c43.jpg)
![小学館文庫 仙川環「感染」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4fcf537dcda4299d15e524ed1051a9f6.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/804f5d050261b3666ea423de338ca4ff-644x1145.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/067c6a3a4eec09284c3afbd457da3bbe-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/804f5d050261b3666ea423de338ca4ff-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6a8bbd8f583af56b77e9067586fbf43c-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4729eb5e39691648aef5d182771438df-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8f174248b8331a4cf720739f7a44b3f3-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb79c321d57027ddc1cafcda86a6c73d-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文6_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/fbbb9bdc315ed949ad05d00c5bd1e35d-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文7_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6b56a6954ba99077b6ffe2af75e46d08-180x320.jpg)
![講談社文庫 村上春樹 アンダーグランウンド 本文8_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/432cdfcc2ca742d146f944d940cbeda6-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/286239e57169f2e75c13f46a4ca87c43-644x1145.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/286239e57169f2e75c13f46a4ca87c43-169x300.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/f221e0dea5b2b83ede56826b8d0cef18-169x300.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/0a12c35a4e194776231ddf0f487d5abf-169x300.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/2b42202e28cc46c51425978f1eb08f20-169x300.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/b7b5cc6c78278d9e95064e83ac71c36d-169x300.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/08dfd025f7e247f155445a314855be4c-169x300.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb77de07cae191366abcab605163c060.jpg)