【メモ】
・いままでに一杯読んできたリリー・フランキー先生の本。この本が一番最初だったか、「誰も知らない名言集」が最初だったか。どっちを先に読んだか覚えていないけれど、大爆笑してイッパツでファンになったのを覚えてる。
・当時すでに有名だったんだろうけれど、僕自身は知らなくて、本でリリー・フランキーを知った。
・ハードカバーで持ってたんだけど、結婚して引っ越す時かなにかに捨てるか売るかしてしまったらしい。なので文庫版を買い直した。という位に面白い。
・下らない話なはずなにに、読んでみるとあまり下らなくない。つまりどういうことかというと、よくわからないけれど、「下らないテーマ」について一生懸命全力でしっかりと書いている。ということなのだと思う。これってまさに「現実」「社会」「世の中」というものの有り様なのではないか?とかとまで思ってしまう。
【本文書き出し】
(「大麻農家の花嫁」13ページ〜より抜粋。)
”
「ああ、コレね。このへんの百姓はみんな、なんだが畑行ぐ時に使っでる。田舎はだだっ広いから、家からはじっごの畑まで行ぐのに時間かがるでしょ。これぐれえ速えぇ車使わねぇど日が暮れぢまうんでね」
ジャリを巻き込んだタイヤから小石をはじく音が大きく車の底に響く。横目でスピードメーターを覗くと針は210km/hを指していた。
「お、お父さん・・・・・・。これは何ていう車なんですか・・・・・・?すごい速いですね・・・・・・」
「ああ、コレね。ランボルギーニっで。知らねぇでしょ東京のひどは。田舎もんの車だがらね。流行らねぇでしょ、今どき」
猛スピードで農道を走るランボルギーニの両脇には見渡す限りのビニールハウスが並んでいる。紀一郎の父はこの辺りの畑はすべて自分の家の畑だと言った。
かなりの距離は走ったはずなのに、あっという間に長田家に到着した。木造の古い建物だった。横に広い平屋。納屋の前にはさっきの車の色違いが2台停めてあった。
体験したことのないスピード感に息を途切れさせながら、多恵子は這い出るように羽のように開くドアを開け、車外に転がり出た。
畑のほうから、作業衣を着て背中に籠を背負った白人の男が3人。紀一郎の父を見つけると頭をペコリと下げる。彼らが近づくと、紀一郎の父はそれぞれの籠に入った葉っぱのようなものを少しづつ手に取り、鼻に近づけながら、何か指示を与えているようだった。白人の視線が多恵子に向く。多恵子は慌てて会釈をすると白人は笑いながら拝むように両手を前で揃えて腰を折った。
「こちらで、働いていらっしゃる方々ですか?」
「ハイ。ドウイタシマシタ」
紀一郎の父から“鈴木”と呼ばれている白人のひとりがそう答えた。他の白人ふたりは“佐藤”“田中”と呼ばれているようだ。
「ああ、コレね。コイツらはオランダの方がら出稼ぎに来でる外人。ウヂの畑はいろいろ専門的な知識もいるで、オランダがら呼んでるの。普段はアムスで百姓やっでたって。ホラ、おめえたち、このすと紀一郎のお見合いに来てぐれだ松井さんだぁ。松井・・・・・・?」
「多恵子、です・・・・・・」
「そう。多恵子さんだぁ」
「タエ、コサン。ハイ。ドウイタシマシタ」。オランダ人はまた手を合わせる…
”
”
表で車の音がした。紀一郎かなと父親が言って三和土の方へ身を乗り出した。多恵子は背筋を伸ばして座り直し、髪に手をやる。入り口から男がふたり入って来た。派手なスーツを着たヤクザ風の男と若い男。紀一郎ではない。
「社長。どうも、お世話になってます」
男はそう言いながら土間に腰掛け煙草をくわえた。若い男がすかさずそれに火を点ける。煙草の煙を吐きながら男は多恵子に目をやったが、すぐにまた話し始めた。
「先日お願いした件。どうにかなりませんかね、無理を承知で今日は来させてもらったんですが、50。いや30でもいい。ウチの方へ回してもらえると助かるんですが。オヤジの方からも是非とのことで」
紀一郎の父はキセルを吸いながら話を聞いていたが、厳しい表情を崩さずに男に言った。
「アンタんところの渡辺さんにはよぐしてもらっでる。しがしね、前も言ったように、今年は天気もずっとこんなだし、納得いぐ草が育っでねえ。この時期にそんだけの数を出すわけにはいがねぇの」
「ですから。今日のところはトップリーヴだけとは申しません。とにかく30キロ。モノが落ちてもとりあえず量があれば・・・・・・」
男がそう言うと、キセルを囲炉裏の隅に叩きつけるドンという音が響いた。多恵子は驚いて背筋が伸びる。
「なんでもええがらというわげにはいがんべや!!ウヂは昔がら、長田の畑の草でねえどと言って下さるお客さんと売させでもらっでる。少し値は張っでも輸入モンにはねえキキがあると言うて下さる!なんでもええがら量を出せど言われて出せるような草は作っでねえづもりだが!!」
「いや!!社長!!そういう意味じゃないんですよ。私は紀一郎さんの方から、そのへん融通して下さると聞いたものですから・・・・・・」
「紀一郎が何ど言うだか知らねぇけんども、今、回せる草は1グラムもねえ!!」
「社長!!いや、そこをなんとか・・・・・・」
紀一郎の父は腕組みをしたまま男たちに背を向けた。男たちはしばらくその背中を見つめた後、また来ますと言い残して帰って行った。多恵子は恐る恐る声を出す。
「あの・・・・・・。今の方たちは・・・・・・?」
「ああ、アレね。なんで言うが・・・・・・アレだ。農協の人だ」
「ああ・・・・・・。農協の・・・・・・」
外に出た男たちは黒のベントレーに乗り込みながら長田の家の玄関の方を一瞥した。
「変わらんなあ。あの社長も」
「やっぱり紀一郎さんと直接話した方が良かったですかね」
「そうだな。三代目はインテリだ。商売を知ってる。社長の作る草は天下一品だが、もうあの人は時代遅れだ。今時はガキでもシャブ喰ってる御時世よ。草の味のわかる客なんざいやしねぇのよ。俺たちも通の人相手に商売してたら干からびちまう。素人やOLやガキに流してシノがなきゃ仕方ねぇ。こっちだって危ない橋渡ってんのよ。奴らにとっちゃ質なんか関係ねぇ。そのへんの枯葉だっていいのよ。紙に巻いてそれだって言っときゃ本当に効いちゃうんだから。怖ぇよ、素人は」
煙草をくわえた男に若い男が火を差し出す。
「またアレですかね。さっきいた女」。若い男が含み笑いで言った。
「お見合いか?三代目の。だろうな、だぶん」
「やってんですねぇ。また」
「でも、今度のはかなりいいんじゃないか?なあ、アレ」
「ですね。そうとうでしたもんね」
「アレは、キテるよなあ。でも、オマエ知ってるか?三代目の前のカミさんってミス・ユニバース日本代表なんだぞ」
「え—!?マジっすか!?それで、なんでまた!?」
「三代目な、あの人、変態なんだ・・・・・・」…
”
【表紙及び冒頭5ページ】
【基本データ】
幻冬舎文庫
平成19年8月10日 初版発行
リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」
ISBN978-4-344-41003-9
”この本、読ませてみたいな”と思ったら
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6a7b4c01911030510fa9cf1b18adcb23-600x600.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/6a7b4c01911030510fa9cf1b18adcb23-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/95afb958e95714ec5fe0ddb18e4caaf9-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/25e5ad2bbaa978f6b6953d8d6d117942-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7bfabe6ede2696fe38d18ae64092d671-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/56491aab2c889694412c00a3098dc957-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「ボロボロになった人へ」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4b53fdb836d4a25c9f4bbaaadefdf8a7-180x320.jpg)
![幻冬舎文庫 リリー・フランキー「増量・誰も知らない名言集 イラスト入り」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/e57ece85c57fc697c8d0f268695105ed.jpg)
![河出文庫 リリー・フランキー「美女と野球」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/054c4740379308b2b9baafdd4ed9abcb.jpg)
![正しい保健体育 みうらじゅん 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/fe8eb09a44cb4c131fc3a8475bed03b2-600x600.jpg)
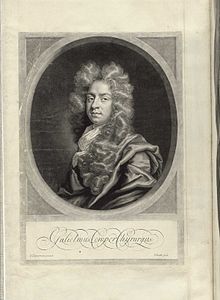
![正しい保健体育 みうらじゅん 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/fe8eb09a44cb4c131fc3a8475bed03b2-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d-600x600.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/c129e945306af75a5e754c9c202be97d-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文1_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/7acbbbd425e5b26784e40790cec66b8e-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文2_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/568915458f31e71b4cc0d2c9f85e8469-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文3_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/8a9cc9d5e3e20eacab99f7a0fd74fe3f-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文4_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/a45e5bdd66128be187843fe1f35e8720-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「果つる底なき」本文5_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/df16c82afd8de2b248066899a5b13034-180x320.jpg)
![講談社文庫 池井戸潤「鉄の骨」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/eb77de07cae191366abcab605163c060.jpg)
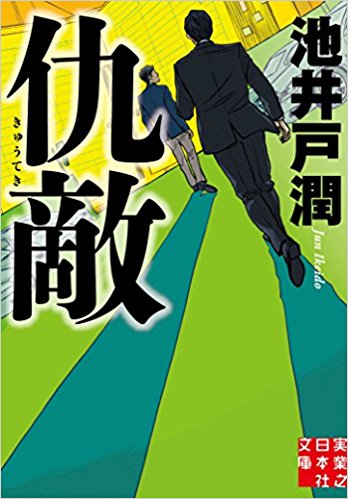
![講談社文庫 池井戸潤 空飛ぶタイヤ 表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/286239e57169f2e75c13f46a4ca87c43.jpg)
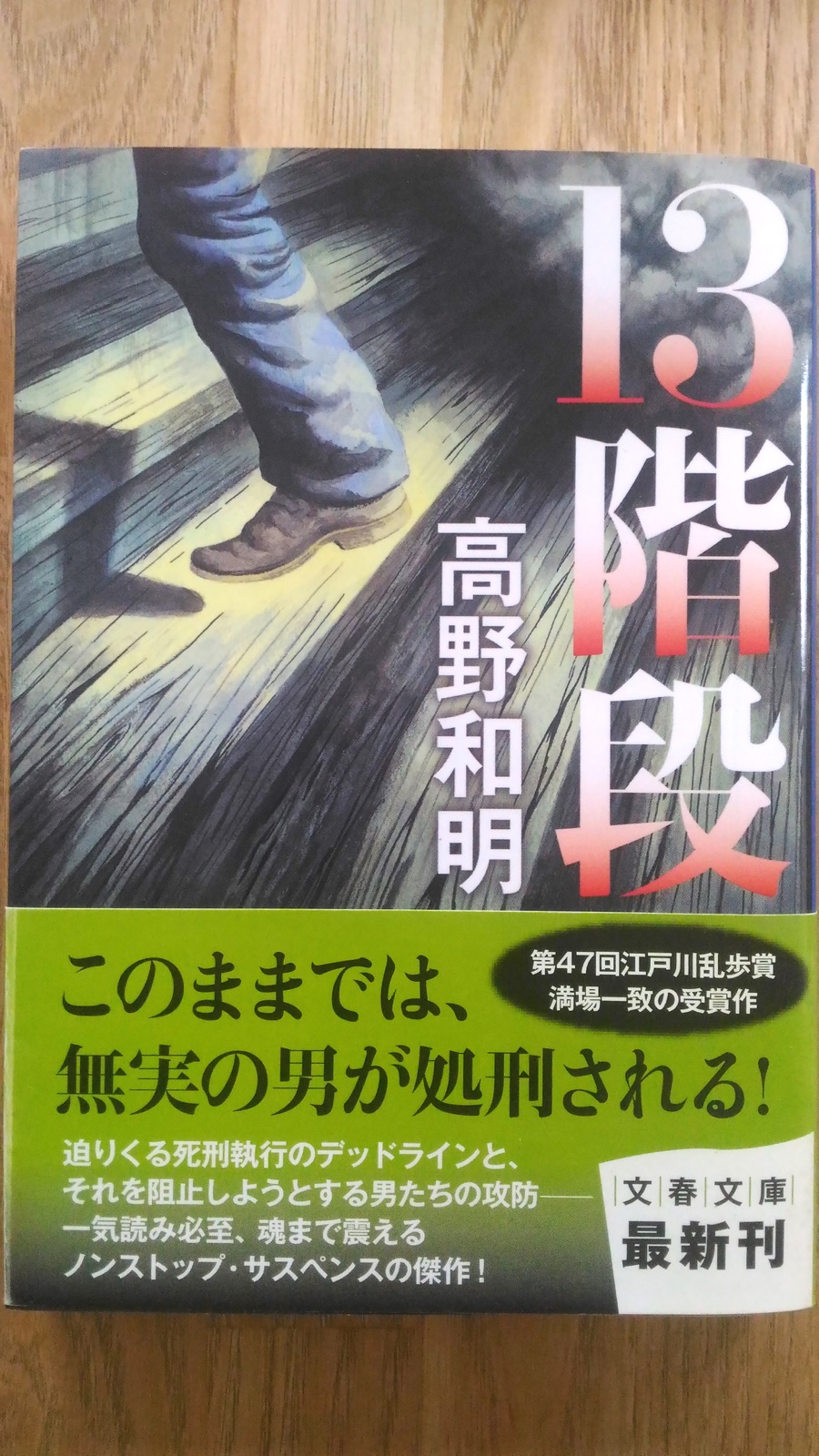
![小学館文庫 仙川環「感染」表紙_[0]](http://www.yomase.org/wordpress/wp-content/uploads/4fcf537dcda4299d15e524ed1051a9f6.jpg)